2010.12.10
直角になって咲いたスパティフィラム
58歳の時に、サラリーマンを辞めて古本屋になった。古本屋になりたいと、前々から考えていたのだ。まず店舗をと考えて、これはという物件に決めようと考えたが、折りしもインターネットが普及し始め、ある方から「今古本屋の店売りは下がる一方だから、まずインターネットから始めてみては」と、アドバイスを頂いた。早速、2000年にホームページを開設。その後古書組合に入って、神田の市場で本を仕入れるようになった。
古本屋になって良かったと思うのは、お客様から、「数年来、母の捜していた本が入手できて、母が大変喜んでいる」とか、「大学院で自分の進むべき道に迷っていた時、頂いた1冊の本で自分の進路を決めました」などの、うれしいメールを頂いた時だ。富山の方が、たった1冊の文庫本を求めて来店し、「もしお宅になかったら、国会図書館で全頁コピーしようと思っていました」と話を聞かせてくれ、ブルガリヤの大学の先生は、文学書をまとめ買いしてくれた。はじめは、「ええ!!古本屋やるの」と抵抗感のあった妻も、今では事務所で一緒に机を並べ、パソコンに向かっている。
古書組合の理事の仕事も、させて頂いた。理事の仕事は、確かにかなりの時間が割かれる。理事会、支部役員会、担当の機関紙編集、経理など神田通いが多かった。私は、本屋の2代目でもなく、本屋に修業したこともなくて、本のこと、組合のことをよく知らなかったが、この仕事を通して、理事の方々と面識が出来、沢山のことを教えていただいた。また全古書連の会合で金沢、京都、仙台に出張、地方の市場・古本屋の疲弊状況に何とも言えない思いもした。
出版不況とか、本のデジタル化とかで、業界にとって厳しい現況だ。何とか、色々手がけたいことは沢山あるのだが、障害も多い。こういったことは、ビジネスにとっては当たりまえのことなのだが・・・。そんな時、事務所の窓をみてびっくりした。驚いた。スパティフィラムの、白い花が咲いていたのだ。それも、小さな窓の窓枠に置いたので、茎は垂直に伸びて上の窓枠にぶつかり、茎を直角にまげその先に白い花を咲かせていたのだ。このスパティフィラムは、娘が開業祝いに事務所に置いてくれたもので、その時は白い花が咲いていたのが、緑色に変わったきり、以来10年間一度も咲いたことがなかったのだ。久しぶりに花が咲き、しかも逆境にめげずに咲いた姿に「がんばりなさい」、と励まされているような気がした。
どんなことがあろうとも、前向きに考え、この仕事を天命と考え、この道を歩み続けたいと思っているのだ。
(この文章は東京新聞(2010年7月7日朝刊)に掲載された原稿に、加筆致しました。)
古本屋になって良かったと思うのは、お客様から、「数年来、母の捜していた本が入手できて、母が大変喜んでいる」とか、「大学院で自分の進むべき道に迷っていた時、頂いた1冊の本で自分の進路を決めました」などの、うれしいメールを頂いた時だ。富山の方が、たった1冊の文庫本を求めて来店し、「もしお宅になかったら、国会図書館で全頁コピーしようと思っていました」と話を聞かせてくれ、ブルガリヤの大学の先生は、文学書をまとめ買いしてくれた。はじめは、「ええ!!古本屋やるの」と抵抗感のあった妻も、今では事務所で一緒に机を並べ、パソコンに向かっている。
古書組合の理事の仕事も、させて頂いた。理事の仕事は、確かにかなりの時間が割かれる。理事会、支部役員会、担当の機関紙編集、経理など神田通いが多かった。私は、本屋の2代目でもなく、本屋に修業したこともなくて、本のこと、組合のことをよく知らなかったが、この仕事を通して、理事の方々と面識が出来、沢山のことを教えていただいた。また全古書連の会合で金沢、京都、仙台に出張、地方の市場・古本屋の疲弊状況に何とも言えない思いもした。
出版不況とか、本のデジタル化とかで、業界にとって厳しい現況だ。何とか、色々手がけたいことは沢山あるのだが、障害も多い。こういったことは、ビジネスにとっては当たりまえのことなのだが・・・。そんな時、事務所の窓をみてびっくりした。驚いた。スパティフィラムの、白い花が咲いていたのだ。それも、小さな窓の窓枠に置いたので、茎は垂直に伸びて上の窓枠にぶつかり、茎を直角にまげその先に白い花を咲かせていたのだ。このスパティフィラムは、娘が開業祝いに事務所に置いてくれたもので、その時は白い花が咲いていたのが、緑色に変わったきり、以来10年間一度も咲いたことがなかったのだ。久しぶりに花が咲き、しかも逆境にめげずに咲いた姿に「がんばりなさい」、と励まされているような気がした。
どんなことがあろうとも、前向きに考え、この仕事を天命と考え、この道を歩み続けたいと思っているのだ。
(この文章は東京新聞(2010年7月7日朝刊)に掲載された原稿に、加筆致しました。)
カテゴリ:書物のまほろば
2010.12.01
自然と人間との闘い 人間同士の闘い そして共生の大切さ
昨年の11月21日から8日間、妻と九州を巡った。 長女のいる北九州を訪ねがてら、私の行ったことのない九州各地を巡ってみたかったのだ。 ルートは、羽田→大分空港→湯布院→別府→小倉→雲仙→長崎→鹿児島→指宿→鹿児島空港→羽田 というものだった。
・自然と人間との闘い
中学校の地理の時間に先ず教わったのは、日本は、島国で火山列島ということだ。以前熊本の阿蘇山に行ったとき、広大な阿蘇の山域そして巨大な噴火口に圧倒されたものだ。
今回その阿蘇山は行かなかったが、九州のあちこちで日本は、火の国、火山国というのをまのあたりにした。別府のホテルで温泉につかり良い気分で、翌日は、別府の地獄めぐりと考えた。でも観光バスでの8箇所の地獄めぐりは、時間もお金もかかりそうなのでやめて、路線バスで、2・3箇所をまわることにした。地獄とは、箱根の大涌谷のように噴煙をあげている温泉噴出口であり「小さな噴火口」なのだ。最初は、海地獄というところで碧い色をした池からもうもうと噴煙を巻き上げていた。次はそこから坂道をあがって10分ほどで坊主地獄。こちらは粘土状の泥水が吹き上がり、それが坊主頭のような形をしているのだ。説明によるとここには以前寺があり、あるとき突然の噴火でここの坊さんも行方不明となってしまったという。帰りのバスを待つ間あたりを眺めると、近くの住宅・病院などのあいだのあちこちから噴煙がたち上がり、もし噴火のような現象が起きたらこの辺は危険との隣あわせと思わざるを得なかった。
小倉の娘の家で2日間過ごし、雲仙に向かった。雲仙のクラッシクな木造のホテルに荷物を置いて、雲仙でも地獄めぐりをする。ここの地獄は別府と違い、全て無料で散策ができる。亜硫酸ガスのような強烈なにおいの中、地獄めぐりをしたが、九州ホテルという名前のホテルの周囲一帯が地獄となっており、九州ホテルの直下から噴煙が巻き上がってもおかしくないと思った。余計な心配かも知れないが、ここも危険との隣り合わせのような気がした。
翌日は、長崎への移動もかねての観光バスだ。まず訪れたのは普賢岳である。バスガイドさんは、自分で画用紙に絵を描いて噴火前の普賢岳、噴火後の普賢岳と紙芝居のように説明してくれた。江戸時代(寛政4年)には噴火で山体崩壊、それによる津波で(島原大変、肥後迷惑と呼ばれた)1万5千人に人がなくなったそうだ。1991年の噴火は、43人の犠牲者を出し記憶に新しい。ロープウェイを降りたところの展望台から素晴らしい海の景色が眺められたが、普賢岳のふもとは、あの火砕流の跡が生々しい。
長崎から鹿児島に向かったが、鹿児島のホテルについてすぐ桜島に向かう。桜島も活火山なのだ。ここでも過去30回以上の噴火が記録され、死者多数とある。桜島ビジターセンターでは、島の人たちが溶岩対策としてシェルターを作り、子どもたちはヘルメットをかぶって通学している様子が紹介されていた。
以上人間は過酷な自然災害に遭遇して、それを乗り越え火山情報なども完備して、火山近くの温泉は観光地となり、沢山の人が体を癒し、山麓の肥沃な土地で農業を営み、自然と共生し自然とともに生きている姿をみてきたが、今後も山や山の動植物との共生が最重要課題なのだと思わされた。
・人間同士の闘い
雲仙から長崎へは観光バスで向かったが、このバスガイドさんが、長崎に到着の前に永井 隆さんの「この子を残して」という本の冒頭を紹介してくれた。永井さんはレントゲン医師で、長崎の原爆で奥さんをなくし、自分も被爆。子どもたちはたまたま実家に居てその難を免れ、父と子3人の生活を送っていたが、被爆をして もうあと僅かの命とわかって書いた文章の冒頭に、
うとうとしていたら、いつの間に遊びから帰ってきたのか、カヤノが冷たいほほを私のほほにくっつけ、しばらくしてから、
「ああ、・・・・・お父さんのにおい」といった。
この子を残して―――この世をやがて私は去らねばならぬのか!
母のにおいを忘れたゆえ、せめて父のにおいなりとも、と恋しがり、私の眠りを見定めて、こっそり近寄る心のいじらしさ。闘いの火に母を奪われ、父の命はようやくとりとめたものの、それさえまもなく失わねばならぬ運命をこの子は知っているのであろうか?
長崎で観光バスは、グラバー園しか行かなかったので、私たちは、荷物を長崎駅のコインロッカーにおいて、市電で平和公園や浦上天主堂の方に向う。爆心地公園では、地下に埋没した、建物や家財の瓦礫が良く見え、爆発のすごさを物語っていた。
長崎から鹿児島へ行き、鹿児島市内では西郷隆盛の私学校跡地というところに、西南戦争時の銃弾の跡が今でも残っており、ちょっと前まで、日本人同士が戦争をしていた様子がよく分った。
鹿児島からはレンタカーを借りて、指宿に向う。途中知覧に立ち寄ってみようと思い海沿いの道から山道に入ったものの あまり車も見かけず、知覧に行く人はいないのかと思いながら特効平和会館に到着。そこの駐車場には、十数台の大型観光バスが止まっていた。特攻平和会館には、戦闘機や若い特攻隊員の生活ぶりや遺品などが展示されており、特攻隊員が母親に宛てた遺書の数々が涙を誘う。さらに別室で、館員の方が当時のいろいろなお話をしてくれ、その30分ほどの話を聴いて涙がとどめなく流れる。館内にある寄せ書きのノートにカナダから来た人が記帳した文章の一説に「never forgotton」と書いてあったのが大変印象的だった。
ちょっと前まで日本人同士が戦争をしていたのですが、今では日本人同士が戦争をするなど考えられないわけです。ルールを守るのが人間で、何かトラブルがあった場合には話し合いをし、決着がつかない場合には裁判という手段もあるし、知恵と努力で戦争を克服する手段が生まれている訳です。悲惨な戦争は、憎しみの連鎖となります。国が違おうと民族が違おうと、政治や宗教対立しようと人間は戦争をしないで対立を克服できるのが人間です。昨今の日本の情勢を危惧し、総ての人間同士が、友に助け合う共生の大切さを痛感しつつ、東京に戻ったものでした。
・自然と人間との闘い
中学校の地理の時間に先ず教わったのは、日本は、島国で火山列島ということだ。以前熊本の阿蘇山に行ったとき、広大な阿蘇の山域そして巨大な噴火口に圧倒されたものだ。
今回その阿蘇山は行かなかったが、九州のあちこちで日本は、火の国、火山国というのをまのあたりにした。別府のホテルで温泉につかり良い気分で、翌日は、別府の地獄めぐりと考えた。でも観光バスでの8箇所の地獄めぐりは、時間もお金もかかりそうなのでやめて、路線バスで、2・3箇所をまわることにした。地獄とは、箱根の大涌谷のように噴煙をあげている温泉噴出口であり「小さな噴火口」なのだ。最初は、海地獄というところで碧い色をした池からもうもうと噴煙を巻き上げていた。次はそこから坂道をあがって10分ほどで坊主地獄。こちらは粘土状の泥水が吹き上がり、それが坊主頭のような形をしているのだ。説明によるとここには以前寺があり、あるとき突然の噴火でここの坊さんも行方不明となってしまったという。帰りのバスを待つ間あたりを眺めると、近くの住宅・病院などのあいだのあちこちから噴煙がたち上がり、もし噴火のような現象が起きたらこの辺は危険との隣あわせと思わざるを得なかった。
小倉の娘の家で2日間過ごし、雲仙に向かった。雲仙のクラッシクな木造のホテルに荷物を置いて、雲仙でも地獄めぐりをする。ここの地獄は別府と違い、全て無料で散策ができる。亜硫酸ガスのような強烈なにおいの中、地獄めぐりをしたが、九州ホテルという名前のホテルの周囲一帯が地獄となっており、九州ホテルの直下から噴煙が巻き上がってもおかしくないと思った。余計な心配かも知れないが、ここも危険との隣り合わせのような気がした。
翌日は、長崎への移動もかねての観光バスだ。まず訪れたのは普賢岳である。バスガイドさんは、自分で画用紙に絵を描いて噴火前の普賢岳、噴火後の普賢岳と紙芝居のように説明してくれた。江戸時代(寛政4年)には噴火で山体崩壊、それによる津波で(島原大変、肥後迷惑と呼ばれた)1万5千人に人がなくなったそうだ。1991年の噴火は、43人の犠牲者を出し記憶に新しい。ロープウェイを降りたところの展望台から素晴らしい海の景色が眺められたが、普賢岳のふもとは、あの火砕流の跡が生々しい。
長崎から鹿児島に向かったが、鹿児島のホテルについてすぐ桜島に向かう。桜島も活火山なのだ。ここでも過去30回以上の噴火が記録され、死者多数とある。桜島ビジターセンターでは、島の人たちが溶岩対策としてシェルターを作り、子どもたちはヘルメットをかぶって通学している様子が紹介されていた。
以上人間は過酷な自然災害に遭遇して、それを乗り越え火山情報なども完備して、火山近くの温泉は観光地となり、沢山の人が体を癒し、山麓の肥沃な土地で農業を営み、自然と共生し自然とともに生きている姿をみてきたが、今後も山や山の動植物との共生が最重要課題なのだと思わされた。
・人間同士の闘い
雲仙から長崎へは観光バスで向かったが、このバスガイドさんが、長崎に到着の前に永井 隆さんの「この子を残して」という本の冒頭を紹介してくれた。永井さんはレントゲン医師で、長崎の原爆で奥さんをなくし、自分も被爆。子どもたちはたまたま実家に居てその難を免れ、父と子3人の生活を送っていたが、被爆をして もうあと僅かの命とわかって書いた文章の冒頭に、
うとうとしていたら、いつの間に遊びから帰ってきたのか、カヤノが冷たいほほを私のほほにくっつけ、しばらくしてから、
「ああ、・・・・・お父さんのにおい」といった。
この子を残して―――この世をやがて私は去らねばならぬのか!
母のにおいを忘れたゆえ、せめて父のにおいなりとも、と恋しがり、私の眠りを見定めて、こっそり近寄る心のいじらしさ。闘いの火に母を奪われ、父の命はようやくとりとめたものの、それさえまもなく失わねばならぬ運命をこの子は知っているのであろうか?
長崎で観光バスは、グラバー園しか行かなかったので、私たちは、荷物を長崎駅のコインロッカーにおいて、市電で平和公園や浦上天主堂の方に向う。爆心地公園では、地下に埋没した、建物や家財の瓦礫が良く見え、爆発のすごさを物語っていた。
長崎から鹿児島へ行き、鹿児島市内では西郷隆盛の私学校跡地というところに、西南戦争時の銃弾の跡が今でも残っており、ちょっと前まで、日本人同士が戦争をしていた様子がよく分った。
鹿児島からはレンタカーを借りて、指宿に向う。途中知覧に立ち寄ってみようと思い海沿いの道から山道に入ったものの あまり車も見かけず、知覧に行く人はいないのかと思いながら特効平和会館に到着。そこの駐車場には、十数台の大型観光バスが止まっていた。特攻平和会館には、戦闘機や若い特攻隊員の生活ぶりや遺品などが展示されており、特攻隊員が母親に宛てた遺書の数々が涙を誘う。さらに別室で、館員の方が当時のいろいろなお話をしてくれ、その30分ほどの話を聴いて涙がとどめなく流れる。館内にある寄せ書きのノートにカナダから来た人が記帳した文章の一説に「never forgotton」と書いてあったのが大変印象的だった。
ちょっと前まで日本人同士が戦争をしていたのですが、今では日本人同士が戦争をするなど考えられないわけです。ルールを守るのが人間で、何かトラブルがあった場合には話し合いをし、決着がつかない場合には裁判という手段もあるし、知恵と努力で戦争を克服する手段が生まれている訳です。悲惨な戦争は、憎しみの連鎖となります。国が違おうと民族が違おうと、政治や宗教対立しようと人間は戦争をしないで対立を克服できるのが人間です。昨今の日本の情勢を危惧し、総ての人間同士が、友に助け合う共生の大切さを痛感しつつ、東京に戻ったものでした。
カテゴリ:書物のまほろば
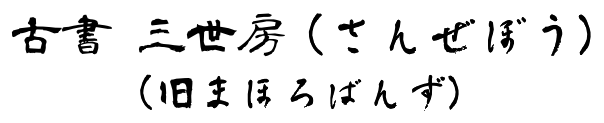
 RSS 2.0
RSS 2.0