2014.05.14
教育勅語について
我が家の前の道路は、小学校の通学路です。4月になりピカピカの1年生が、みんなと一緒に登校しはしめました。我が家の2階の孫にも、そのピカピカの1年生がいます。当初1週間ほど、登校は父兄と上級生と一緒の集団登校、帰りは先生と一緒に下校です。嫁から、あの人が校長先生と教えてもらいましたが、70歳の私から見れば「若いお兄ちゃん」という感じがしました。私の小学校の卒業時の校長先生は、年配でひげをはやした風格のある先生でした。
大阪の二女の男の子は、小学4年生。孫はやっと男の先生になったと喜んでいましたが、私の娘いわく、その男の先生は、去年学校を卒業したばかりで、何か頼りない感じがするし、「好きな食べ物はスイーツで、趣味は、美味しいスイーツを食べながらおしゃべりすること、なんだって」、と電話で話していました。「スイーツ男子」という言葉があるようです。
北九州の長女宅の長女は、高校2年生となり、ワンランク上のクラスを目指していたけど上にいけなかったそうで、成績により、クラスが変わるというのもずいぶんコクな話という感じもしましたが、受験戦争は私たちも通って来た道。大いに揉まれることも、大事なことと思ったものでした。
さて、先日、東京新聞を見て「やっぱり」と思いました。安倍流教育改革で、ますます現場が疲弊し「よい先生が消える」という見出しでした。それは、第一次安倍内閣の改正教育基本法では手ぬるいとした安倍首相が、愛国心をさらに強調。 「お国のために」の洗脳を、次々と進めているとの記事でした。沖縄の竹富町の教科書問題。この育鵬社の教科書をつかっている横浜市のベテラン教員は、「政府が進めるこの教科書は、改憲を誘導し、お国のために立派な国民になれと、マインドコントロールをしようとしているようだと」、批判していました。
政治が教育に介入しては、現場が大変です。ちいさな規模の学校ほど、教員が少なく、負担が大きい。とりわけ若い教員は雑務を押し付けられやすく、教科書を研究したり考えたりする余裕をなくし、国が強要する教科書通りの授業をやらせようとしている。これでは、安倍流教育改革の行きつく先は、公立学校から良い教員が消える、あるいはマニュアル通りの教員ばかりになるという記事でした。
安倍首相の盟友下村文部大臣は、「教育勅語」の復活を目指しているようです。
戦後何度も「教育勅語」の話が浮上し、東郷平八郎が登場したりしました。 戦前、教育勅語を暗記させられた人の中には、あれは良かったという人が何人もいます。確かに、親に孝行、兄弟仲良く、夫婦相和は、良いのですが、最後で「一旦緩急あれば義勇に奉じ」、つまりいざまさかの時には、お国のために進んで戦争に行けというものです。
日本の戦国時代には武士が群雄割拠して、戦争の繰り返しでた。今の日本国内でたとえば、東京都と千葉県が境界争いで武器を持って戦うなんてことは考えられません。話し合いかどうしても決着しなければ、裁判で決着を図ればよい訳です。
世界各国でも、もう少し時間が必要かもしれませんが、話し合いで解決する努力を重ねれば、戦闘機やミサイルも必要なくなります。政治家は、人間の命を大切にすべきですし、外国との戦争ばかりを考えず、世界各国がともに助け合う努力が必要です。
そして我々も、政治に無関心であってはならず、どうあるべきかを考え、発言し、我々が、政治家を動かしてゆくことが大切です。
超格差社会がどんどん進展していますが、我々自身も、「自立自助」を忘れず、困難な社会を生き抜いて、次の時代にバトンタッチして行く必要があると考えています。
◆教育勅語 軸物3点 額1点
教育勅語図解(大正6年大日本国民教育会・表層の部分切れ・補修)
漢文掛け軸(桐箱・玉渚宮松茂書)
御勅語(桐箱入り・横長)
額入(40×68センチ)
合計で、38,800円です。どうぞ、よろしくお願い致します。
大阪の二女の男の子は、小学4年生。孫はやっと男の先生になったと喜んでいましたが、私の娘いわく、その男の先生は、去年学校を卒業したばかりで、何か頼りない感じがするし、「好きな食べ物はスイーツで、趣味は、美味しいスイーツを食べながらおしゃべりすること、なんだって」、と電話で話していました。「スイーツ男子」という言葉があるようです。
北九州の長女宅の長女は、高校2年生となり、ワンランク上のクラスを目指していたけど上にいけなかったそうで、成績により、クラスが変わるというのもずいぶんコクな話という感じもしましたが、受験戦争は私たちも通って来た道。大いに揉まれることも、大事なことと思ったものでした。
さて、先日、東京新聞を見て「やっぱり」と思いました。安倍流教育改革で、ますます現場が疲弊し「よい先生が消える」という見出しでした。それは、第一次安倍内閣の改正教育基本法では手ぬるいとした安倍首相が、愛国心をさらに強調。 「お国のために」の洗脳を、次々と進めているとの記事でした。沖縄の竹富町の教科書問題。この育鵬社の教科書をつかっている横浜市のベテラン教員は、「政府が進めるこの教科書は、改憲を誘導し、お国のために立派な国民になれと、マインドコントロールをしようとしているようだと」、批判していました。
政治が教育に介入しては、現場が大変です。ちいさな規模の学校ほど、教員が少なく、負担が大きい。とりわけ若い教員は雑務を押し付けられやすく、教科書を研究したり考えたりする余裕をなくし、国が強要する教科書通りの授業をやらせようとしている。これでは、安倍流教育改革の行きつく先は、公立学校から良い教員が消える、あるいはマニュアル通りの教員ばかりになるという記事でした。
安倍首相の盟友下村文部大臣は、「教育勅語」の復活を目指しているようです。
戦後何度も「教育勅語」の話が浮上し、東郷平八郎が登場したりしました。 戦前、教育勅語を暗記させられた人の中には、あれは良かったという人が何人もいます。確かに、親に孝行、兄弟仲良く、夫婦相和は、良いのですが、最後で「一旦緩急あれば義勇に奉じ」、つまりいざまさかの時には、お国のために進んで戦争に行けというものです。
日本の戦国時代には武士が群雄割拠して、戦争の繰り返しでた。今の日本国内でたとえば、東京都と千葉県が境界争いで武器を持って戦うなんてことは考えられません。話し合いかどうしても決着しなければ、裁判で決着を図ればよい訳です。
世界各国でも、もう少し時間が必要かもしれませんが、話し合いで解決する努力を重ねれば、戦闘機やミサイルも必要なくなります。政治家は、人間の命を大切にすべきですし、外国との戦争ばかりを考えず、世界各国がともに助け合う努力が必要です。
そして我々も、政治に無関心であってはならず、どうあるべきかを考え、発言し、我々が、政治家を動かしてゆくことが大切です。
超格差社会がどんどん進展していますが、我々自身も、「自立自助」を忘れず、困難な社会を生き抜いて、次の時代にバトンタッチして行く必要があると考えています。
◆教育勅語 軸物3点 額1点
教育勅語図解(大正6年大日本国民教育会・表層の部分切れ・補修)
漢文掛け軸(桐箱・玉渚宮松茂書)
御勅語(桐箱入り・横長)
額入(40×68センチ)
合計で、38,800円です。どうぞ、よろしくお願い致します。
カテゴリ:書物のまほろば
2012.12.18
火宅喩あるいはタイタニック症候群
11月の日曜日に、妻と二人で深川のお不動さんに行ってきました。深川のお不動さんと云うのは、千葉の成田山新勝寺の別院で、私は、まだ行ったことがありませんでした。確かその近くに富岡八幡宮があり、そこは子どものときに父親に連れられて行ったことがあり、朱塗りの社殿をもう一度観たいと思っていました。(朱塗りの社殿は、絵葉書の記憶かもしれませんが・・・)
地下鉄の門前仲町からでると、ちょっとした門前町の風情を楽しみ、本堂に向かいました。本堂の中には参拝順路あり、入口近くの旧本堂の場所には大きな木造の、おねがい不動尊が安置され、初穂料1ヶ月間1万円以上と大きく書いてありました、本堂はどこなのかとみると、旧本堂の横に位置し、護摩壇と階段状の長椅子が見えました。千葉の成田さんの本堂は畳敷きですが、こちらは椅子席でしかも階段状です。この新本堂は4階建てで順路に従って一回りすると、なかなか見応えのある場所でした。またお賽銭銭箱の多いのには、びっくりしました。ざっと計算しても500や600ではなく、1000以上はあると思われました。また仏像の奉納は、3寸で50万円、1尺で500万円とありました。昔サラリーマンの時に、千葉の成田山に大塔を建立するというので、黒い袈裟を着たお坊さんが二人で、会社に寄進の依頼にきた時を思い出しました。成田さんは商売が上手だと誰かが言っていましたが、考えられ得るすべての場所にお賽銭箱を置く企業努力(?)、これは商人として学ぶべきことなのかもしれないと思ったものでした。
順路を回り終えて本堂に戻ると、丁度護摩修業の時間になっていましたので、椅子に座って参拝することにしました。千葉の成田山とほぼ同じやり方で、大太鼓が鳴り響き、お坊さんの1団がホラ貝の先導で入場、お経をあげながら護摩が焚かれます。最後のお説教で終了です。
お不動さんを出て、お昼は、深川飯を食べました。物の本によると、明治時代、深川飯と云うのは最下層の人が食べるもので、臭いので鼻をつまみながら食べたとありましたが、鼻をつままなくても、美味しく食べられました。
富岡八幡宮は、お不動さんのすぐ隣りにありました。境内では、骨董市が開かれており、社殿に向かうと中で結婚式が行われて、何かうれしいような気分を頂きました。
帰りに喫茶店に入って、一休みです。そこでお不動さんで頂いた雑誌を開いてみました。この雑誌の巻頭言に有名な「火宅の話」がでていました。法華経の中にでてくる火宅喩の話です。
或るところに長者の邸宅があったのですが、そこが火事になってしまう。中にいた子どもたちが遊びに夢中なって、家が火事になっていることに気がつかない。父親は早く逃げるようにと促すが、子どもたちは聞き入れようとしない。そこで父親は一計を案じて「外 には羊・鹿・牛の牽く車があるぞ」と呼びかけると子どもたちは火宅から走りでてきた。
と云う話ですが、この成田さんの雑誌では原発についてふれており、今原発について国論が二分し、論争が行なわれている。どちらにも言い分・利があるようにみえるが、原発温存論者の視点は、火宅喩の子供たちと同じで、目先の生活とか原発関係者の利益のことしか見えていない。原発の安全性が仮に100パーセント確保されたとしても、放射性廃棄物の処理方法・廃棄場所な何一つきまっていない。子孫が放射性廃棄物に埋もれるのを、み仏たちはお許しにならない、というものでした。タイタニック症候群というのも一緒で、乗客も船員たちも世界一の豪華客船に興奮し、気が付けば氷山と衝突してしまったのです。
帰りの電車の中で今日一日を振り返り、私も火宅の子供たちや、タイタニック症候群であってはならないと思いつつ家路につきました。日本では原発に反対する人が7割だそうですが、原発を推進する自民党が第一党になり、その辺のギャップは、少選挙区制のひずみなのか,多数の政党が乱立したせいなのか、棄権者が多かったのか・・・
子どもたちに少しでも、負の遺産を減らしたいと思っているのですが、まだまだやることがいっぱいあるのです。
在庫品
『法華経大講座 全12巻揃』
小林一郎 著 久保田正文 増補/日新出版/昭和41発行/\18,900 (本体 \18,000)
5版 函イタミ ビニールカバー 蔵書印 小口シミ 第3巻・10巻本文ヤケ 少線引き
地下鉄の門前仲町からでると、ちょっとした門前町の風情を楽しみ、本堂に向かいました。本堂の中には参拝順路あり、入口近くの旧本堂の場所には大きな木造の、おねがい不動尊が安置され、初穂料1ヶ月間1万円以上と大きく書いてありました、本堂はどこなのかとみると、旧本堂の横に位置し、護摩壇と階段状の長椅子が見えました。千葉の成田さんの本堂は畳敷きですが、こちらは椅子席でしかも階段状です。この新本堂は4階建てで順路に従って一回りすると、なかなか見応えのある場所でした。またお賽銭銭箱の多いのには、びっくりしました。ざっと計算しても500や600ではなく、1000以上はあると思われました。また仏像の奉納は、3寸で50万円、1尺で500万円とありました。昔サラリーマンの時に、千葉の成田山に大塔を建立するというので、黒い袈裟を着たお坊さんが二人で、会社に寄進の依頼にきた時を思い出しました。成田さんは商売が上手だと誰かが言っていましたが、考えられ得るすべての場所にお賽銭箱を置く企業努力(?)、これは商人として学ぶべきことなのかもしれないと思ったものでした。
順路を回り終えて本堂に戻ると、丁度護摩修業の時間になっていましたので、椅子に座って参拝することにしました。千葉の成田山とほぼ同じやり方で、大太鼓が鳴り響き、お坊さんの1団がホラ貝の先導で入場、お経をあげながら護摩が焚かれます。最後のお説教で終了です。
お不動さんを出て、お昼は、深川飯を食べました。物の本によると、明治時代、深川飯と云うのは最下層の人が食べるもので、臭いので鼻をつまみながら食べたとありましたが、鼻をつままなくても、美味しく食べられました。
富岡八幡宮は、お不動さんのすぐ隣りにありました。境内では、骨董市が開かれており、社殿に向かうと中で結婚式が行われて、何かうれしいような気分を頂きました。
帰りに喫茶店に入って、一休みです。そこでお不動さんで頂いた雑誌を開いてみました。この雑誌の巻頭言に有名な「火宅の話」がでていました。法華経の中にでてくる火宅喩の話です。
或るところに長者の邸宅があったのですが、そこが火事になってしまう。中にいた子どもたちが遊びに夢中なって、家が火事になっていることに気がつかない。父親は早く逃げるようにと促すが、子どもたちは聞き入れようとしない。そこで父親は一計を案じて「外 には羊・鹿・牛の牽く車があるぞ」と呼びかけると子どもたちは火宅から走りでてきた。
と云う話ですが、この成田さんの雑誌では原発についてふれており、今原発について国論が二分し、論争が行なわれている。どちらにも言い分・利があるようにみえるが、原発温存論者の視点は、火宅喩の子供たちと同じで、目先の生活とか原発関係者の利益のことしか見えていない。原発の安全性が仮に100パーセント確保されたとしても、放射性廃棄物の処理方法・廃棄場所な何一つきまっていない。子孫が放射性廃棄物に埋もれるのを、み仏たちはお許しにならない、というものでした。タイタニック症候群というのも一緒で、乗客も船員たちも世界一の豪華客船に興奮し、気が付けば氷山と衝突してしまったのです。
帰りの電車の中で今日一日を振り返り、私も火宅の子供たちや、タイタニック症候群であってはならないと思いつつ家路につきました。日本では原発に反対する人が7割だそうですが、原発を推進する自民党が第一党になり、その辺のギャップは、少選挙区制のひずみなのか,多数の政党が乱立したせいなのか、棄権者が多かったのか・・・
子どもたちに少しでも、負の遺産を減らしたいと思っているのですが、まだまだやることがいっぱいあるのです。
在庫品
『法華経大講座 全12巻揃』
小林一郎 著 久保田正文 増補/日新出版/昭和41発行/\18,900 (本体 \18,000)
5版 函イタミ ビニールカバー 蔵書印 小口シミ 第3巻・10巻本文ヤケ 少線引き
カテゴリ:書物のまほろば
2010.12.10
直角になって咲いたスパティフィラム
58歳の時に、サラリーマンを辞めて古本屋になった。古本屋になりたいと、前々から考えていたのだ。まず店舗をと考えて、これはという物件に決めようと考えたが、折りしもインターネットが普及し始め、ある方から「今古本屋の店売りは下がる一方だから、まずインターネットから始めてみては」と、アドバイスを頂いた。早速、2000年にホームページを開設。その後古書組合に入って、神田の市場で本を仕入れるようになった。
古本屋になって良かったと思うのは、お客様から、「数年来、母の捜していた本が入手できて、母が大変喜んでいる」とか、「大学院で自分の進むべき道に迷っていた時、頂いた1冊の本で自分の進路を決めました」などの、うれしいメールを頂いた時だ。富山の方が、たった1冊の文庫本を求めて来店し、「もしお宅になかったら、国会図書館で全頁コピーしようと思っていました」と話を聞かせてくれ、ブルガリヤの大学の先生は、文学書をまとめ買いしてくれた。はじめは、「ええ!!古本屋やるの」と抵抗感のあった妻も、今では事務所で一緒に机を並べ、パソコンに向かっている。
古書組合の理事の仕事も、させて頂いた。理事の仕事は、確かにかなりの時間が割かれる。理事会、支部役員会、担当の機関紙編集、経理など神田通いが多かった。私は、本屋の2代目でもなく、本屋に修業したこともなくて、本のこと、組合のことをよく知らなかったが、この仕事を通して、理事の方々と面識が出来、沢山のことを教えていただいた。また全古書連の会合で金沢、京都、仙台に出張、地方の市場・古本屋の疲弊状況に何とも言えない思いもした。
出版不況とか、本のデジタル化とかで、業界にとって厳しい現況だ。何とか、色々手がけたいことは沢山あるのだが、障害も多い。こういったことは、ビジネスにとっては当たりまえのことなのだが・・・。そんな時、事務所の窓をみてびっくりした。驚いた。スパティフィラムの、白い花が咲いていたのだ。それも、小さな窓の窓枠に置いたので、茎は垂直に伸びて上の窓枠にぶつかり、茎を直角にまげその先に白い花を咲かせていたのだ。このスパティフィラムは、娘が開業祝いに事務所に置いてくれたもので、その時は白い花が咲いていたのが、緑色に変わったきり、以来10年間一度も咲いたことがなかったのだ。久しぶりに花が咲き、しかも逆境にめげずに咲いた姿に「がんばりなさい」、と励まされているような気がした。
どんなことがあろうとも、前向きに考え、この仕事を天命と考え、この道を歩み続けたいと思っているのだ。
(この文章は東京新聞(2010年7月7日朝刊)に掲載された原稿に、加筆致しました。)
古本屋になって良かったと思うのは、お客様から、「数年来、母の捜していた本が入手できて、母が大変喜んでいる」とか、「大学院で自分の進むべき道に迷っていた時、頂いた1冊の本で自分の進路を決めました」などの、うれしいメールを頂いた時だ。富山の方が、たった1冊の文庫本を求めて来店し、「もしお宅になかったら、国会図書館で全頁コピーしようと思っていました」と話を聞かせてくれ、ブルガリヤの大学の先生は、文学書をまとめ買いしてくれた。はじめは、「ええ!!古本屋やるの」と抵抗感のあった妻も、今では事務所で一緒に机を並べ、パソコンに向かっている。
古書組合の理事の仕事も、させて頂いた。理事の仕事は、確かにかなりの時間が割かれる。理事会、支部役員会、担当の機関紙編集、経理など神田通いが多かった。私は、本屋の2代目でもなく、本屋に修業したこともなくて、本のこと、組合のことをよく知らなかったが、この仕事を通して、理事の方々と面識が出来、沢山のことを教えていただいた。また全古書連の会合で金沢、京都、仙台に出張、地方の市場・古本屋の疲弊状況に何とも言えない思いもした。
出版不況とか、本のデジタル化とかで、業界にとって厳しい現況だ。何とか、色々手がけたいことは沢山あるのだが、障害も多い。こういったことは、ビジネスにとっては当たりまえのことなのだが・・・。そんな時、事務所の窓をみてびっくりした。驚いた。スパティフィラムの、白い花が咲いていたのだ。それも、小さな窓の窓枠に置いたので、茎は垂直に伸びて上の窓枠にぶつかり、茎を直角にまげその先に白い花を咲かせていたのだ。このスパティフィラムは、娘が開業祝いに事務所に置いてくれたもので、その時は白い花が咲いていたのが、緑色に変わったきり、以来10年間一度も咲いたことがなかったのだ。久しぶりに花が咲き、しかも逆境にめげずに咲いた姿に「がんばりなさい」、と励まされているような気がした。
どんなことがあろうとも、前向きに考え、この仕事を天命と考え、この道を歩み続けたいと思っているのだ。
(この文章は東京新聞(2010年7月7日朝刊)に掲載された原稿に、加筆致しました。)
カテゴリ:書物のまほろば
2010.12.01
自然と人間との闘い 人間同士の闘い そして共生の大切さ
昨年の11月21日から8日間、妻と九州を巡った。 長女のいる北九州を訪ねがてら、私の行ったことのない九州各地を巡ってみたかったのだ。 ルートは、羽田→大分空港→湯布院→別府→小倉→雲仙→長崎→鹿児島→指宿→鹿児島空港→羽田 というものだった。
・自然と人間との闘い
中学校の地理の時間に先ず教わったのは、日本は、島国で火山列島ということだ。以前熊本の阿蘇山に行ったとき、広大な阿蘇の山域そして巨大な噴火口に圧倒されたものだ。
今回その阿蘇山は行かなかったが、九州のあちこちで日本は、火の国、火山国というのをまのあたりにした。別府のホテルで温泉につかり良い気分で、翌日は、別府の地獄めぐりと考えた。でも観光バスでの8箇所の地獄めぐりは、時間もお金もかかりそうなのでやめて、路線バスで、2・3箇所をまわることにした。地獄とは、箱根の大涌谷のように噴煙をあげている温泉噴出口であり「小さな噴火口」なのだ。最初は、海地獄というところで碧い色をした池からもうもうと噴煙を巻き上げていた。次はそこから坂道をあがって10分ほどで坊主地獄。こちらは粘土状の泥水が吹き上がり、それが坊主頭のような形をしているのだ。説明によるとここには以前寺があり、あるとき突然の噴火でここの坊さんも行方不明となってしまったという。帰りのバスを待つ間あたりを眺めると、近くの住宅・病院などのあいだのあちこちから噴煙がたち上がり、もし噴火のような現象が起きたらこの辺は危険との隣あわせと思わざるを得なかった。
小倉の娘の家で2日間過ごし、雲仙に向かった。雲仙のクラッシクな木造のホテルに荷物を置いて、雲仙でも地獄めぐりをする。ここの地獄は別府と違い、全て無料で散策ができる。亜硫酸ガスのような強烈なにおいの中、地獄めぐりをしたが、九州ホテルという名前のホテルの周囲一帯が地獄となっており、九州ホテルの直下から噴煙が巻き上がってもおかしくないと思った。余計な心配かも知れないが、ここも危険との隣り合わせのような気がした。
翌日は、長崎への移動もかねての観光バスだ。まず訪れたのは普賢岳である。バスガイドさんは、自分で画用紙に絵を描いて噴火前の普賢岳、噴火後の普賢岳と紙芝居のように説明してくれた。江戸時代(寛政4年)には噴火で山体崩壊、それによる津波で(島原大変、肥後迷惑と呼ばれた)1万5千人に人がなくなったそうだ。1991年の噴火は、43人の犠牲者を出し記憶に新しい。ロープウェイを降りたところの展望台から素晴らしい海の景色が眺められたが、普賢岳のふもとは、あの火砕流の跡が生々しい。
長崎から鹿児島に向かったが、鹿児島のホテルについてすぐ桜島に向かう。桜島も活火山なのだ。ここでも過去30回以上の噴火が記録され、死者多数とある。桜島ビジターセンターでは、島の人たちが溶岩対策としてシェルターを作り、子どもたちはヘルメットをかぶって通学している様子が紹介されていた。
以上人間は過酷な自然災害に遭遇して、それを乗り越え火山情報なども完備して、火山近くの温泉は観光地となり、沢山の人が体を癒し、山麓の肥沃な土地で農業を営み、自然と共生し自然とともに生きている姿をみてきたが、今後も山や山の動植物との共生が最重要課題なのだと思わされた。
・人間同士の闘い
雲仙から長崎へは観光バスで向かったが、このバスガイドさんが、長崎に到着の前に永井 隆さんの「この子を残して」という本の冒頭を紹介してくれた。永井さんはレントゲン医師で、長崎の原爆で奥さんをなくし、自分も被爆。子どもたちはたまたま実家に居てその難を免れ、父と子3人の生活を送っていたが、被爆をして もうあと僅かの命とわかって書いた文章の冒頭に、
うとうとしていたら、いつの間に遊びから帰ってきたのか、カヤノが冷たいほほを私のほほにくっつけ、しばらくしてから、
「ああ、・・・・・お父さんのにおい」といった。
この子を残して―――この世をやがて私は去らねばならぬのか!
母のにおいを忘れたゆえ、せめて父のにおいなりとも、と恋しがり、私の眠りを見定めて、こっそり近寄る心のいじらしさ。闘いの火に母を奪われ、父の命はようやくとりとめたものの、それさえまもなく失わねばならぬ運命をこの子は知っているのであろうか?
長崎で観光バスは、グラバー園しか行かなかったので、私たちは、荷物を長崎駅のコインロッカーにおいて、市電で平和公園や浦上天主堂の方に向う。爆心地公園では、地下に埋没した、建物や家財の瓦礫が良く見え、爆発のすごさを物語っていた。
長崎から鹿児島へ行き、鹿児島市内では西郷隆盛の私学校跡地というところに、西南戦争時の銃弾の跡が今でも残っており、ちょっと前まで、日本人同士が戦争をしていた様子がよく分った。
鹿児島からはレンタカーを借りて、指宿に向う。途中知覧に立ち寄ってみようと思い海沿いの道から山道に入ったものの あまり車も見かけず、知覧に行く人はいないのかと思いながら特効平和会館に到着。そこの駐車場には、十数台の大型観光バスが止まっていた。特攻平和会館には、戦闘機や若い特攻隊員の生活ぶりや遺品などが展示されており、特攻隊員が母親に宛てた遺書の数々が涙を誘う。さらに別室で、館員の方が当時のいろいろなお話をしてくれ、その30分ほどの話を聴いて涙がとどめなく流れる。館内にある寄せ書きのノートにカナダから来た人が記帳した文章の一説に「never forgotton」と書いてあったのが大変印象的だった。
ちょっと前まで日本人同士が戦争をしていたのですが、今では日本人同士が戦争をするなど考えられないわけです。ルールを守るのが人間で、何かトラブルがあった場合には話し合いをし、決着がつかない場合には裁判という手段もあるし、知恵と努力で戦争を克服する手段が生まれている訳です。悲惨な戦争は、憎しみの連鎖となります。国が違おうと民族が違おうと、政治や宗教対立しようと人間は戦争をしないで対立を克服できるのが人間です。昨今の日本の情勢を危惧し、総ての人間同士が、友に助け合う共生の大切さを痛感しつつ、東京に戻ったものでした。
・自然と人間との闘い
中学校の地理の時間に先ず教わったのは、日本は、島国で火山列島ということだ。以前熊本の阿蘇山に行ったとき、広大な阿蘇の山域そして巨大な噴火口に圧倒されたものだ。
今回その阿蘇山は行かなかったが、九州のあちこちで日本は、火の国、火山国というのをまのあたりにした。別府のホテルで温泉につかり良い気分で、翌日は、別府の地獄めぐりと考えた。でも観光バスでの8箇所の地獄めぐりは、時間もお金もかかりそうなのでやめて、路線バスで、2・3箇所をまわることにした。地獄とは、箱根の大涌谷のように噴煙をあげている温泉噴出口であり「小さな噴火口」なのだ。最初は、海地獄というところで碧い色をした池からもうもうと噴煙を巻き上げていた。次はそこから坂道をあがって10分ほどで坊主地獄。こちらは粘土状の泥水が吹き上がり、それが坊主頭のような形をしているのだ。説明によるとここには以前寺があり、あるとき突然の噴火でここの坊さんも行方不明となってしまったという。帰りのバスを待つ間あたりを眺めると、近くの住宅・病院などのあいだのあちこちから噴煙がたち上がり、もし噴火のような現象が起きたらこの辺は危険との隣あわせと思わざるを得なかった。
小倉の娘の家で2日間過ごし、雲仙に向かった。雲仙のクラッシクな木造のホテルに荷物を置いて、雲仙でも地獄めぐりをする。ここの地獄は別府と違い、全て無料で散策ができる。亜硫酸ガスのような強烈なにおいの中、地獄めぐりをしたが、九州ホテルという名前のホテルの周囲一帯が地獄となっており、九州ホテルの直下から噴煙が巻き上がってもおかしくないと思った。余計な心配かも知れないが、ここも危険との隣り合わせのような気がした。
翌日は、長崎への移動もかねての観光バスだ。まず訪れたのは普賢岳である。バスガイドさんは、自分で画用紙に絵を描いて噴火前の普賢岳、噴火後の普賢岳と紙芝居のように説明してくれた。江戸時代(寛政4年)には噴火で山体崩壊、それによる津波で(島原大変、肥後迷惑と呼ばれた)1万5千人に人がなくなったそうだ。1991年の噴火は、43人の犠牲者を出し記憶に新しい。ロープウェイを降りたところの展望台から素晴らしい海の景色が眺められたが、普賢岳のふもとは、あの火砕流の跡が生々しい。
長崎から鹿児島に向かったが、鹿児島のホテルについてすぐ桜島に向かう。桜島も活火山なのだ。ここでも過去30回以上の噴火が記録され、死者多数とある。桜島ビジターセンターでは、島の人たちが溶岩対策としてシェルターを作り、子どもたちはヘルメットをかぶって通学している様子が紹介されていた。
以上人間は過酷な自然災害に遭遇して、それを乗り越え火山情報なども完備して、火山近くの温泉は観光地となり、沢山の人が体を癒し、山麓の肥沃な土地で農業を営み、自然と共生し自然とともに生きている姿をみてきたが、今後も山や山の動植物との共生が最重要課題なのだと思わされた。
・人間同士の闘い
雲仙から長崎へは観光バスで向かったが、このバスガイドさんが、長崎に到着の前に永井 隆さんの「この子を残して」という本の冒頭を紹介してくれた。永井さんはレントゲン医師で、長崎の原爆で奥さんをなくし、自分も被爆。子どもたちはたまたま実家に居てその難を免れ、父と子3人の生活を送っていたが、被爆をして もうあと僅かの命とわかって書いた文章の冒頭に、
うとうとしていたら、いつの間に遊びから帰ってきたのか、カヤノが冷たいほほを私のほほにくっつけ、しばらくしてから、
「ああ、・・・・・お父さんのにおい」といった。
この子を残して―――この世をやがて私は去らねばならぬのか!
母のにおいを忘れたゆえ、せめて父のにおいなりとも、と恋しがり、私の眠りを見定めて、こっそり近寄る心のいじらしさ。闘いの火に母を奪われ、父の命はようやくとりとめたものの、それさえまもなく失わねばならぬ運命をこの子は知っているのであろうか?
長崎で観光バスは、グラバー園しか行かなかったので、私たちは、荷物を長崎駅のコインロッカーにおいて、市電で平和公園や浦上天主堂の方に向う。爆心地公園では、地下に埋没した、建物や家財の瓦礫が良く見え、爆発のすごさを物語っていた。
長崎から鹿児島へ行き、鹿児島市内では西郷隆盛の私学校跡地というところに、西南戦争時の銃弾の跡が今でも残っており、ちょっと前まで、日本人同士が戦争をしていた様子がよく分った。
鹿児島からはレンタカーを借りて、指宿に向う。途中知覧に立ち寄ってみようと思い海沿いの道から山道に入ったものの あまり車も見かけず、知覧に行く人はいないのかと思いながら特効平和会館に到着。そこの駐車場には、十数台の大型観光バスが止まっていた。特攻平和会館には、戦闘機や若い特攻隊員の生活ぶりや遺品などが展示されており、特攻隊員が母親に宛てた遺書の数々が涙を誘う。さらに別室で、館員の方が当時のいろいろなお話をしてくれ、その30分ほどの話を聴いて涙がとどめなく流れる。館内にある寄せ書きのノートにカナダから来た人が記帳した文章の一説に「never forgotton」と書いてあったのが大変印象的だった。
ちょっと前まで日本人同士が戦争をしていたのですが、今では日本人同士が戦争をするなど考えられないわけです。ルールを守るのが人間で、何かトラブルがあった場合には話し合いをし、決着がつかない場合には裁判という手段もあるし、知恵と努力で戦争を克服する手段が生まれている訳です。悲惨な戦争は、憎しみの連鎖となります。国が違おうと民族が違おうと、政治や宗教対立しようと人間は戦争をしないで対立を克服できるのが人間です。昨今の日本の情勢を危惧し、総ての人間同士が、友に助け合う共生の大切さを痛感しつつ、東京に戻ったものでした。
カテゴリ:書物のまほろば
2006.08.27
父の従軍日誌
私の手元に、古びた1枚の写真がある。四つ切りの割と大きな物で、写真の下の方に万年筆で「ブロードウェイマンション」と説明書きがある。私はこの写真を他の数枚と一緒に、以前勤務していた会社の写真部の先輩から頂いたものだ。その時は、何とも思わなかったが、この「ブロードウェイマンション」が気になってきた。
その後何かの機会に、ブロードウェイマンションは上海にあって、児玉誉士夫や川島芳子住んだ事もあると知った。解放前の中国には、上海を含め28箇所の租界があり、現在の上海にも、当時の建物がほぼそのまま残されていると言う。
私は、ブロードウェイマンションについて調べていくうちに、「上海敵前上陸」(三好捷三著 図書出版社刊)という本に出合った。この本には、ブロードウェイマンションは登場せず、最後迄凄惨な戦闘模様の連続であった。
昭和12年9月3日に上海の外港呉淞(ウースン)に投錨、上陸。上陸してみたら、岸壁には、一面見渡す限りの死体の山で、土も見えない位だったという。10日前に上陸した名古屋第三師団の将兵の変わり果てた姿だった。その犠牲者は1万人と言われている。
「3日以内に羅店鎮の本体に合流すべし」という軍命令で、20キロ、戦争がなければ一日でも充分な行程だが、実際には30日かかり、著者のいた200名の中隊が20名に減少してしまった。そのうち、一緒に上陸した仲間は皆戦闘で死傷し自分一人となり、まわりはあとからの補充兵となってしまったのだ。
食糧もひどく、輸送船では三度三度大根の切干しのみのおかず、上陸して六日間は食糧の支給が無く缶詰をあけると日露戦争時代のもので、臭くて食べられなかった話。ご飯を炊く水が無く、只でさえ臭いクリークの水を汲もうとクリークに行くと、中国兵の死体が異臭を放って浮いており、死体を押しやって、元に戻らないうちに水をすくって、ご飯を炊いたが、臭くてどうにも食べられなかった話。食糧の配給というので、行って見たらカンピョウばかりだった事。一方後方の旅団司令部では、車座になって宴会をやっていたこと。装備も日本の手榴弾は、日露戦争時代のもので、自爆して死傷者が出て、皆捨ててしまったこと。一方中国側は、手榴弾も最新式の優秀品、他の装備も優れたものだった。
連日の死闘による疲労に加え食料不足でよれよれになりながら、さらに南京追撃戦で320キロの追撃に入ったが、赤痢になり、落伍して野戦病院に入れられ、一命を取り止める事ができたのだ。何回もの戦闘をくぐりぬけ奇跡的に生還出来たのは、彼の何としても生きて帰るという強い信念と幸運が重なった結果だろう。私は、この本から、したたかな生き方を学び、勇気を与えられた。
一方私の父は、どんな戦争体験をしたのだろうか。私の父鶴吉は明治43年に生まれ、昭和47年61歳で他界した。この頃やっと父の時代、父の生き方に興味を抱くようになった。
そんな時、小学5年生の私の長男が、夏休みの自由学習のテーマを考えあぐねていたので、「おじいちゃんの戦争体験について、おばあちゃんから聞いてそれをまとめてみたらどうか」と話した。私のヒントから長男は模造紙に地図を書き、母の話を書き入れた。母は、次のようなメモを息子に渡していた。
昭和16年7月に召集で、市川国府台に入隊してすぐ爪と髪を渡され、それから満州の牡丹江に行き、その年の12月8日に大東亜戦争が始まる。それから半年位便りなし。初めてジャワより便りあり、大変うれしかった。それからどの位かジャワに居て、今度は日本に帰るので、シンガポールを通って来る間、時々アメリカ軍が出没していたそうです。そのまま満州に戻り、17年12月病気で日本に帰り、除隊になりました。もう少し満州にいたら、戦争に負けて、ロシアに連れて行かれる処でした。家に帰っても、空襲になると警備召集で、家には居られません。戦争は考えただけでも恐ろしいと思う。
一番はじめは、北支応召。
子供の宿題から、私は初めて父の従軍状況が分かって来た。さらに母に尋ねると、三冊従軍日記を出してきた。その三冊の手帳には、昭和12年の第1回目の召集から、16年の2回目の召集の分も、時々途切れているが、綺麗な字で克明に記録されていた。
叔父などに訪ねてみて、最初に父が召集されたのは、昭和12年7月7日盧溝橋事件のすぐあとの7月20日である。母のメモの「一ばんはじめは北支応召」と書いてあった処だ。まだ結婚前である。「上海敵前上陸」の著者三好氏は、同年8月に招集で上海に向かったのだ。まさに同じ時期に父は、北支にあって戦っていたのだ。
第一冊目の「陣中日誌」という表題のついた手帳は、昭和13年の1月17日から始まっており、途中でぬけている時もあるが、11月4日で終了している。自動車部隊として、大雪に会ったり、3月13日には、迫撃砲、手榴弾、機銃等で奇襲を受け戦闘約4時間、4名の同僚が戦死している。戦死者は火葬にされ、父は戦死者の位牌を書いている。
○ 3月20日
所隊ハ車弐十両、矢後隊六車両焼却ス 援護ノ歩兵部隊は全滅ス(五十名戦死百名位ノ負傷)所隊十名の犠牲者ヲ出ス
○ 3月29日
六時半 村野部隊及宮本部隊約177車両ニテ歩兵2ヶ中隊工兵1ヶ小隊ノ援護ニテ、敵陣ヲモノトモセズ通過ス 敵約三千名見受ケル
といったように、平遙、介休、太原と云った地名が出て、あちこちに移動露営をしたようだ。
第二冊目は、16年の2回目の召集が決まる前の簡閲点呼から始まっている。友人知人が召集を受け、母と万一の場合を考えて、眠られぬ夜があり、そして勤務先の建築現場(父は建築会社に勤務していた)で兄から召集令状を持ってきたという電話を受ける。出征の挨拶をすませ、夜母が涙を出すが、出発の朝は、
「さと(私の母の名)モ全ク覚悟ガ出来タ様子。涙一ツ出サズ隊マデ見送ラル 前回と違イ万歳ノ声一ツナク 非常ニ気軽ナルモ淋シサヲ感ズ」と記している。
そして瀬戸内海を航行、大連、牡丹江、白門子と移動。途中、カケ麻雀の嫌疑をかけられ心を痛め、ビンタに不愉快な思いをし、12月8日は「英米国に対シ宣戦ノ詔勅下ル」と記し、隊内の興奮振りを伝えている。
満州から南方に移動となり、台湾、フィリピンを経て、3月1日ジャワ敵前上陸をする。前日の日記は次のように書かれている。
最初ノ大キナ空爆ヲ受ケ強力ナル威力ノ爆弾ニ見舞ワレ乍ラ、昨晩ハ十日月位ノ良イ月夜ヨヲ眺メ乍ラ故郷ヲ偲ブ時 急ニ遺言状マデ稿メタクナル ソレデ母上ノ事ヲ子供ノ事、妻、将来等今ニナッテ色々ト心配ス 2月28日 11時
日記を原稿用紙に書き写してみたら、800字詰め原稿用紙で143枚となった。私は、この日記の空白の時を穴埋めすべく、今「大東亜戦史ジャワ作戦」(陸軍省企画、昭和17年刊)や蘭印諸島(福島種経著、昭和17年刊)を読んでいる。
現在の我々は、平和で安逸な生活に埋没してしまっているのではないだろうか。戦後四十年を過ぎ、戦争体験をまとめた出版物は減少し、また以前出された好著でも新刊書店からは姿を消してしまっている。古書店でも見つけにくいのが現状だ。
このままでは貴重な戦争体験が風化されていってしまうのではないだろうか。私は戦争という凄惨の極みの中の記録から強く生きる勇気、生への執念を学んだ。これからも、現代史を知る意味で、昭和の戦争記録を読み続けたいし、かつ後世の世代に正しく語り伝える義務を痛感している。
その後何かの機会に、ブロードウェイマンションは上海にあって、児玉誉士夫や川島芳子住んだ事もあると知った。解放前の中国には、上海を含め28箇所の租界があり、現在の上海にも、当時の建物がほぼそのまま残されていると言う。
私は、ブロードウェイマンションについて調べていくうちに、「上海敵前上陸」(三好捷三著 図書出版社刊)という本に出合った。この本には、ブロードウェイマンションは登場せず、最後迄凄惨な戦闘模様の連続であった。
昭和12年9月3日に上海の外港呉淞(ウースン)に投錨、上陸。上陸してみたら、岸壁には、一面見渡す限りの死体の山で、土も見えない位だったという。10日前に上陸した名古屋第三師団の将兵の変わり果てた姿だった。その犠牲者は1万人と言われている。
「3日以内に羅店鎮の本体に合流すべし」という軍命令で、20キロ、戦争がなければ一日でも充分な行程だが、実際には30日かかり、著者のいた200名の中隊が20名に減少してしまった。そのうち、一緒に上陸した仲間は皆戦闘で死傷し自分一人となり、まわりはあとからの補充兵となってしまったのだ。
食糧もひどく、輸送船では三度三度大根の切干しのみのおかず、上陸して六日間は食糧の支給が無く缶詰をあけると日露戦争時代のもので、臭くて食べられなかった話。ご飯を炊く水が無く、只でさえ臭いクリークの水を汲もうとクリークに行くと、中国兵の死体が異臭を放って浮いており、死体を押しやって、元に戻らないうちに水をすくって、ご飯を炊いたが、臭くてどうにも食べられなかった話。食糧の配給というので、行って見たらカンピョウばかりだった事。一方後方の旅団司令部では、車座になって宴会をやっていたこと。装備も日本の手榴弾は、日露戦争時代のもので、自爆して死傷者が出て、皆捨ててしまったこと。一方中国側は、手榴弾も最新式の優秀品、他の装備も優れたものだった。
連日の死闘による疲労に加え食料不足でよれよれになりながら、さらに南京追撃戦で320キロの追撃に入ったが、赤痢になり、落伍して野戦病院に入れられ、一命を取り止める事ができたのだ。何回もの戦闘をくぐりぬけ奇跡的に生還出来たのは、彼の何としても生きて帰るという強い信念と幸運が重なった結果だろう。私は、この本から、したたかな生き方を学び、勇気を与えられた。
一方私の父は、どんな戦争体験をしたのだろうか。私の父鶴吉は明治43年に生まれ、昭和47年61歳で他界した。この頃やっと父の時代、父の生き方に興味を抱くようになった。
そんな時、小学5年生の私の長男が、夏休みの自由学習のテーマを考えあぐねていたので、「おじいちゃんの戦争体験について、おばあちゃんから聞いてそれをまとめてみたらどうか」と話した。私のヒントから長男は模造紙に地図を書き、母の話を書き入れた。母は、次のようなメモを息子に渡していた。
昭和16年7月に召集で、市川国府台に入隊してすぐ爪と髪を渡され、それから満州の牡丹江に行き、その年の12月8日に大東亜戦争が始まる。それから半年位便りなし。初めてジャワより便りあり、大変うれしかった。それからどの位かジャワに居て、今度は日本に帰るので、シンガポールを通って来る間、時々アメリカ軍が出没していたそうです。そのまま満州に戻り、17年12月病気で日本に帰り、除隊になりました。もう少し満州にいたら、戦争に負けて、ロシアに連れて行かれる処でした。家に帰っても、空襲になると警備召集で、家には居られません。戦争は考えただけでも恐ろしいと思う。
一番はじめは、北支応召。
子供の宿題から、私は初めて父の従軍状況が分かって来た。さらに母に尋ねると、三冊従軍日記を出してきた。その三冊の手帳には、昭和12年の第1回目の召集から、16年の2回目の召集の分も、時々途切れているが、綺麗な字で克明に記録されていた。
叔父などに訪ねてみて、最初に父が召集されたのは、昭和12年7月7日盧溝橋事件のすぐあとの7月20日である。母のメモの「一ばんはじめは北支応召」と書いてあった処だ。まだ結婚前である。「上海敵前上陸」の著者三好氏は、同年8月に招集で上海に向かったのだ。まさに同じ時期に父は、北支にあって戦っていたのだ。
第一冊目の「陣中日誌」という表題のついた手帳は、昭和13年の1月17日から始まっており、途中でぬけている時もあるが、11月4日で終了している。自動車部隊として、大雪に会ったり、3月13日には、迫撃砲、手榴弾、機銃等で奇襲を受け戦闘約4時間、4名の同僚が戦死している。戦死者は火葬にされ、父は戦死者の位牌を書いている。
○ 3月20日
所隊ハ車弐十両、矢後隊六車両焼却ス 援護ノ歩兵部隊は全滅ス(五十名戦死百名位ノ負傷)所隊十名の犠牲者ヲ出ス
○ 3月29日
六時半 村野部隊及宮本部隊約177車両ニテ歩兵2ヶ中隊工兵1ヶ小隊ノ援護ニテ、敵陣ヲモノトモセズ通過ス 敵約三千名見受ケル
といったように、平遙、介休、太原と云った地名が出て、あちこちに移動露営をしたようだ。
第二冊目は、16年の2回目の召集が決まる前の簡閲点呼から始まっている。友人知人が召集を受け、母と万一の場合を考えて、眠られぬ夜があり、そして勤務先の建築現場(父は建築会社に勤務していた)で兄から召集令状を持ってきたという電話を受ける。出征の挨拶をすませ、夜母が涙を出すが、出発の朝は、
「さと(私の母の名)モ全ク覚悟ガ出来タ様子。涙一ツ出サズ隊マデ見送ラル 前回と違イ万歳ノ声一ツナク 非常ニ気軽ナルモ淋シサヲ感ズ」と記している。
そして瀬戸内海を航行、大連、牡丹江、白門子と移動。途中、カケ麻雀の嫌疑をかけられ心を痛め、ビンタに不愉快な思いをし、12月8日は「英米国に対シ宣戦ノ詔勅下ル」と記し、隊内の興奮振りを伝えている。
満州から南方に移動となり、台湾、フィリピンを経て、3月1日ジャワ敵前上陸をする。前日の日記は次のように書かれている。
最初ノ大キナ空爆ヲ受ケ強力ナル威力ノ爆弾ニ見舞ワレ乍ラ、昨晩ハ十日月位ノ良イ月夜ヨヲ眺メ乍ラ故郷ヲ偲ブ時 急ニ遺言状マデ稿メタクナル ソレデ母上ノ事ヲ子供ノ事、妻、将来等今ニナッテ色々ト心配ス 2月28日 11時
日記を原稿用紙に書き写してみたら、800字詰め原稿用紙で143枚となった。私は、この日記の空白の時を穴埋めすべく、今「大東亜戦史ジャワ作戦」(陸軍省企画、昭和17年刊)や蘭印諸島(福島種経著、昭和17年刊)を読んでいる。
現在の我々は、平和で安逸な生活に埋没してしまっているのではないだろうか。戦後四十年を過ぎ、戦争体験をまとめた出版物は減少し、また以前出された好著でも新刊書店からは姿を消してしまっている。古書店でも見つけにくいのが現状だ。
このままでは貴重な戦争体験が風化されていってしまうのではないだろうか。私は戦争という凄惨の極みの中の記録から強く生きる勇気、生への執念を学んだ。これからも、現代史を知る意味で、昭和の戦争記録を読み続けたいし、かつ後世の世代に正しく語り伝える義務を痛感している。
日本古書通信 1987年7月号
カテゴリ:書物のまほろば
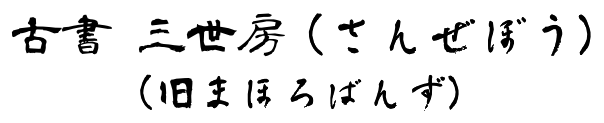
 RSS 2.0
RSS 2.0