2005.12.01
呼吸法
2000年の11月にインターネットの古書店を開業させて頂いた。丁度その頃、関節リウマチになった。手の指が脹れてきたのだ。駅前の整形外科に行って、検査の末に間接リウマチと診断され、治療の難しい、膠原病じゃなくてよかったですねとも言われた。
関節リュウマチと診断されて、家族から専門医に診てもらった方が良いのでは、と言われ、ネットで、リウマチ友の会という存在を知った。そこに電話をして相談したら、練馬という立地から、新宿の大きな大学病院を教えて頂いた。この病院には、「膠原病リウマチ痛風センター」というのがあり、これらの病気に関しては、日本では、一番大きな規模の病院ではないかと思う。診察室が15ぐらいあり、とにかく患者も先生も多いのだ。
この病院に月一回の割合で、もう4年も通っているのだが、この間に色々なことがあった。通院して1年以上たって、2回目のレントゲンを撮った。その結果を見て、先生は、にっこり笑いながら、「やっぱり関節リウマチですね。」と言った。にっこり笑ったのは、自分の診断に間違いはなかったということで、思わず、にっこりしたのだろうが、私にとっては、たとえ誤診であっても、もっと簡単に直る病気の方が嬉しかったのだが・・・。 レントゲンで見る指の骨が、以前と比べると少し欠けていたのだった。
そして、薬の副作用には、随分と悩まされた。診察室の壁に模造紙が貼ってあり、そこに沢山のリウマチ薬のサンプルが貼りつけてある。その中で患者の症状にあわせて、弱い薬から強い薬を選択していくのだ、私は、薬の影響でしょっちゅう、気持ち悪くなったり、吐き気がしたりして事務所で寝込んでしまったことも何回かあった。 その都度薬を替えてもらうのだが、何度目かに、副作用を訴えると、先生曰く、「どうしましょうか?」ときたのだ。私はこの言葉に、一瞬「頼りにならない先生だと」という思いだった。しかし時間がたつにつれ、現代に医療姿勢は、患者の意思を尊重するものであり、患者の考えを確認したうえで、対処するのでは、と思うようになり、あわせて病気は医者が治すのではなく患者本人の病気に対する気持ちが大切と思うようになった。つまり、人まかせでなく、自分の病気は自分で直すという気構えが一番肝心なのだと悟ったものでした。
リウマチがなかなか直らない病気であることを体験して、民間の治療法にもトライしている。今迄試したものは、あざらしのオイル(オイルシール)、サメの軟骨、アロエべラ、核酸などなど。他には、鍼、ラジウム、温泉など今後色々トライしてみたいと思っている。
そんな折に“呼吸法”で、病気が良くなるという言葉を耳にした。そこで、「丹田呼吸法」 村木弘昌著 三笠書房刊 を読んでみた。 心臓病、糖尿病、ガンなど万病に良いとされるこの、丹田呼吸法は、遠くお釈迦様に起因するのだそうだ。お釈迦様は、色々荒行を試みたがこれらの行が、悟りとは無縁であることを知り、かくして、菩提樹の下に座すこと三か月、悟りを得る。このときの呼吸法が、「出る息を長く吸う方は短く」という呼吸法だったそうだ。
この本では、さらに白隠禅師の「夜船閑話(やぜんかんな)」にふれ、内観法、軟酥の法にふれている。軟酥の法は、まさしくイメージトレーニングである。白隠禅師は、これを、山城の国の山奥に住んでいる白幽仙人から教わり、これを実行することによって、鍼も灸もいらないと言っているのだ。
私は、この本の中で紹介されている一番簡単な「三呼一吸法」を毎日続けている。まだ始めて二か月。発病以来四年もたっているので、すぐに直るわけはない。「継続は力なり」で、続けている。
なおこの本のなかでも、紹介されていた、西野バレー団の西野皓三著「西野流呼吸法」 講談社刊、や龍村修著「深い呼吸でからだが変わる」など呼吸法は人間の健康、活力と大いにかかわっているのだということが良く分かった。
関節リュウマチと診断されて、家族から専門医に診てもらった方が良いのでは、と言われ、ネットで、リウマチ友の会という存在を知った。そこに電話をして相談したら、練馬という立地から、新宿の大きな大学病院を教えて頂いた。この病院には、「膠原病リウマチ痛風センター」というのがあり、これらの病気に関しては、日本では、一番大きな規模の病院ではないかと思う。診察室が15ぐらいあり、とにかく患者も先生も多いのだ。
この病院に月一回の割合で、もう4年も通っているのだが、この間に色々なことがあった。通院して1年以上たって、2回目のレントゲンを撮った。その結果を見て、先生は、にっこり笑いながら、「やっぱり関節リウマチですね。」と言った。にっこり笑ったのは、自分の診断に間違いはなかったということで、思わず、にっこりしたのだろうが、私にとっては、たとえ誤診であっても、もっと簡単に直る病気の方が嬉しかったのだが・・・。 レントゲンで見る指の骨が、以前と比べると少し欠けていたのだった。
そして、薬の副作用には、随分と悩まされた。診察室の壁に模造紙が貼ってあり、そこに沢山のリウマチ薬のサンプルが貼りつけてある。その中で患者の症状にあわせて、弱い薬から強い薬を選択していくのだ、私は、薬の影響でしょっちゅう、気持ち悪くなったり、吐き気がしたりして事務所で寝込んでしまったことも何回かあった。 その都度薬を替えてもらうのだが、何度目かに、副作用を訴えると、先生曰く、「どうしましょうか?」ときたのだ。私はこの言葉に、一瞬「頼りにならない先生だと」という思いだった。しかし時間がたつにつれ、現代に医療姿勢は、患者の意思を尊重するものであり、患者の考えを確認したうえで、対処するのでは、と思うようになり、あわせて病気は医者が治すのではなく患者本人の病気に対する気持ちが大切と思うようになった。つまり、人まかせでなく、自分の病気は自分で直すという気構えが一番肝心なのだと悟ったものでした。
リウマチがなかなか直らない病気であることを体験して、民間の治療法にもトライしている。今迄試したものは、あざらしのオイル(オイルシール)、サメの軟骨、アロエべラ、核酸などなど。他には、鍼、ラジウム、温泉など今後色々トライしてみたいと思っている。
そんな折に“呼吸法”で、病気が良くなるという言葉を耳にした。そこで、「丹田呼吸法」 村木弘昌著 三笠書房刊 を読んでみた。 心臓病、糖尿病、ガンなど万病に良いとされるこの、丹田呼吸法は、遠くお釈迦様に起因するのだそうだ。お釈迦様は、色々荒行を試みたがこれらの行が、悟りとは無縁であることを知り、かくして、菩提樹の下に座すこと三か月、悟りを得る。このときの呼吸法が、「出る息を長く吸う方は短く」という呼吸法だったそうだ。
この本では、さらに白隠禅師の「夜船閑話(やぜんかんな)」にふれ、内観法、軟酥の法にふれている。軟酥の法は、まさしくイメージトレーニングである。白隠禅師は、これを、山城の国の山奥に住んでいる白幽仙人から教わり、これを実行することによって、鍼も灸もいらないと言っているのだ。
私は、この本の中で紹介されている一番簡単な「三呼一吸法」を毎日続けている。まだ始めて二か月。発病以来四年もたっているので、すぐに直るわけはない。「継続は力なり」で、続けている。
なおこの本のなかでも、紹介されていた、西野バレー団の西野皓三著「西野流呼吸法」 講談社刊、や龍村修著「深い呼吸でからだが変わる」など呼吸法は人間の健康、活力と大いにかかわっているのだということが良く分かった。
カテゴリ:書物のまほろば
2005.11.01
ぼくの老後
昨年3月に愛知県の友人から、1通の手紙をもらいました。この方は、大変な読書家なのですが、「やっとひいきの作家が見つかりました」と、手紙に、ある作家のエッセイをコピーして、同封してくれました。そのエッセイは、「ぼくの老後」と題されており、その論旨は、次のような内容です。
自分は、貧乏人だが、いい加減な人間ではない。ちゃんとした生き方を持っている。今まで、一生懸命働いてきたので、死ぬまでの時間を15年間と逆算して、どうして過ごすか、と考えると、旨いものを食べ続けながら、本を読んで死のうと思う。死ぬ時もっていけない家にお金をかけたり、高価な衣服を買ってもしょうがない。
食べ物は、自宅の庭で野菜を作り、好きな毛がにや、マツタケも堪能しているし、特に紅ジャケが、好きで北洋物しか食べない。外出して列車に乗るとき紅ジャケ弁当がないと、タクシーで百貨店を巡り、紅ジャケ弁当を探し、どうしてもないときには、生の切り身を買って、その場で焼いてもらう。
お金が、無くなったら、今住んでいる家を売って安アパートを借りて、旨いものを食い続けたい。
というような内容のものでした。誠に、さわやかな感じで、共感の持てるエッセイでした。
特にこのエッセイを読んだあとに、一つの出来事に遭遇したのです。それは、わが家の庭で、ご近所の生協の皆さんが、商品の仕分けをしている時に、私は、お花見に行きませんかと誘ったのでした。そうしたら、急に行こう話しがまとまりましたので、お隣りの70代のご主人にも声を掛けてみました。そのご主人は、今日は調子が良くないけれど、明日、調子が良かったら行きましょうとの返事で、さらに、夕方わざわざ出席しますと伝えにきてくれました。その時の四方山話で、自分の女房は、耳が遠くて不自由しているし、私が先に死ぬわけにはいかないし、もうひと暴れしたいと繰り返し言っておられました。「もうひと暴れ」ってどういう意味だろうと思ったものでしたが、その晩、そのご主人は、脳梗塞で倒れ救急車で病院に運ばれ、帰らぬ人となってしまいました。
友人からもらったエッセイや、このお隣のご主人のことから、なるほどやりたいことをやって死ぬのが一番と思ったものでした。
このエッセイを書かれた作家は、小檜山博さんで、彼の小説「地の音」を読んでみました。もちろん小説ですから、彼の、実体験とは、異なるのでしょうが、でも彼の実体験を土台に書かれた小説でしょう。
その小説では、戦後の厳しい環境のなかの北海道で、貧しい農家に生まれて、中学を出たら働けと言われたにもかかわらず高校に進学。親もとを離れて高校の寮生活をするが、繰り返し親から、授業料が払えないからと退学を迫られ続けたことが、書かれています。
さらに、3度の食事にも不自由をして、寮生が、集団で近くの畑から、農作物を盗み、農家の人が、クレームをつけにくると、「わが校の生徒にそんな、不届き者はいない」とかばう先生。その先生は、授業料滞納が続くと、先の分まで払った生徒の授業料を調整して、当面のつじつまを合わせてくれる。
もし私が、こんな状況になったらすぐに学校をやめて、働いて、当座の生活費を稼いだろうに、こういった壮絶な高校生活を経ての人生を類推すると、「旨いものを食い続けて、本を読みながら死にたい」というのは、充分分かりすぎるくらいに分ったのでした。
しかしながら、頭の中にひっかることが、いくつかあったのです。まず、旨いものを、食い続けて、やりたいことをやって、死ぬのもいいけれど、もし、病気で寝たきりになったりしたら、どうなるのだろうか? 長期入院となったら病院代も大変だし、結局子供たちが出し合って、病院代を支払っているというケースもよく耳にする。昨年は、妻が病気で入退院を繰り返し、医療費には考えさせられたし、おまけにわが家は、老朽化しており、すぐにでも、手をつけなければならない状態なのだ。子孫に美田は要らないけれど、ある程度の老後の備えがないとまずいと、気づいてその旨、エッセイを送ってくれた友人に手紙を出すと、彼から早速返事が来て、私の言いたかったのは、早めに老後の備えをしなさいということですと言われてしまった。
そうなのだ。私には、そういった人生設計が著しく欠けていたことに気づかされたのです。さらに人生ということを考えると、祖先、親、子供、孫といった流れのなかで、中間ランナーとして、子供達や、孫達に伝えなければならいことも沢山あるはずだ。さらに自分を取り巻く周囲の皆様に、少しでもお役立ちが出来て、はじめて私の存在価値が出てくるのでは、と思い至ったのです。
小檜山博さんは、実績も残しそしてあざやかな人生を送られているが、他人に迷惑をかけっぱなしの私は、自分のことだけでなく、さらに少しでも周囲への配慮をし、支えあってこそ人生と改めて、思うようになったのでした。
自分は、貧乏人だが、いい加減な人間ではない。ちゃんとした生き方を持っている。今まで、一生懸命働いてきたので、死ぬまでの時間を15年間と逆算して、どうして過ごすか、と考えると、旨いものを食べ続けながら、本を読んで死のうと思う。死ぬ時もっていけない家にお金をかけたり、高価な衣服を買ってもしょうがない。
食べ物は、自宅の庭で野菜を作り、好きな毛がにや、マツタケも堪能しているし、特に紅ジャケが、好きで北洋物しか食べない。外出して列車に乗るとき紅ジャケ弁当がないと、タクシーで百貨店を巡り、紅ジャケ弁当を探し、どうしてもないときには、生の切り身を買って、その場で焼いてもらう。
お金が、無くなったら、今住んでいる家を売って安アパートを借りて、旨いものを食い続けたい。
というような内容のものでした。誠に、さわやかな感じで、共感の持てるエッセイでした。
特にこのエッセイを読んだあとに、一つの出来事に遭遇したのです。それは、わが家の庭で、ご近所の生協の皆さんが、商品の仕分けをしている時に、私は、お花見に行きませんかと誘ったのでした。そうしたら、急に行こう話しがまとまりましたので、お隣りの70代のご主人にも声を掛けてみました。そのご主人は、今日は調子が良くないけれど、明日、調子が良かったら行きましょうとの返事で、さらに、夕方わざわざ出席しますと伝えにきてくれました。その時の四方山話で、自分の女房は、耳が遠くて不自由しているし、私が先に死ぬわけにはいかないし、もうひと暴れしたいと繰り返し言っておられました。「もうひと暴れ」ってどういう意味だろうと思ったものでしたが、その晩、そのご主人は、脳梗塞で倒れ救急車で病院に運ばれ、帰らぬ人となってしまいました。
友人からもらったエッセイや、このお隣のご主人のことから、なるほどやりたいことをやって死ぬのが一番と思ったものでした。
このエッセイを書かれた作家は、小檜山博さんで、彼の小説「地の音」を読んでみました。もちろん小説ですから、彼の、実体験とは、異なるのでしょうが、でも彼の実体験を土台に書かれた小説でしょう。
その小説では、戦後の厳しい環境のなかの北海道で、貧しい農家に生まれて、中学を出たら働けと言われたにもかかわらず高校に進学。親もとを離れて高校の寮生活をするが、繰り返し親から、授業料が払えないからと退学を迫られ続けたことが、書かれています。
さらに、3度の食事にも不自由をして、寮生が、集団で近くの畑から、農作物を盗み、農家の人が、クレームをつけにくると、「わが校の生徒にそんな、不届き者はいない」とかばう先生。その先生は、授業料滞納が続くと、先の分まで払った生徒の授業料を調整して、当面のつじつまを合わせてくれる。
もし私が、こんな状況になったらすぐに学校をやめて、働いて、当座の生活費を稼いだろうに、こういった壮絶な高校生活を経ての人生を類推すると、「旨いものを食い続けて、本を読みながら死にたい」というのは、充分分かりすぎるくらいに分ったのでした。
しかしながら、頭の中にひっかることが、いくつかあったのです。まず、旨いものを、食い続けて、やりたいことをやって、死ぬのもいいけれど、もし、病気で寝たきりになったりしたら、どうなるのだろうか? 長期入院となったら病院代も大変だし、結局子供たちが出し合って、病院代を支払っているというケースもよく耳にする。昨年は、妻が病気で入退院を繰り返し、医療費には考えさせられたし、おまけにわが家は、老朽化しており、すぐにでも、手をつけなければならない状態なのだ。子孫に美田は要らないけれど、ある程度の老後の備えがないとまずいと、気づいてその旨、エッセイを送ってくれた友人に手紙を出すと、彼から早速返事が来て、私の言いたかったのは、早めに老後の備えをしなさいということですと言われてしまった。
そうなのだ。私には、そういった人生設計が著しく欠けていたことに気づかされたのです。さらに人生ということを考えると、祖先、親、子供、孫といった流れのなかで、中間ランナーとして、子供達や、孫達に伝えなければならいことも沢山あるはずだ。さらに自分を取り巻く周囲の皆様に、少しでもお役立ちが出来て、はじめて私の存在価値が出てくるのでは、と思い至ったのです。
小檜山博さんは、実績も残しそしてあざやかな人生を送られているが、他人に迷惑をかけっぱなしの私は、自分のことだけでなく、さらに少しでも周囲への配慮をし、支えあってこそ人生と改めて、思うようになったのでした。
カテゴリ:書物のまほろば
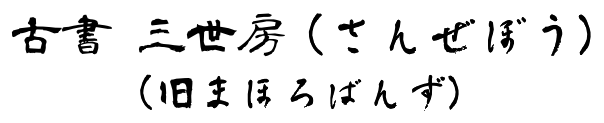
 RSS 2.0
RSS 2.0