2017.02.08
亀戸天神の三つの橋と川上澄生の私家版「御朱印船」
亀戸天神の三つの橋と川上澄生の私家版「御朱印船」
今年の初詣は、地元の春日神社と亀戸天神へ行ってきた。毎年長男の家族と一緒のお参りだが、今年は春日神社へは一緒に行けたが、亀戸天神は日程が合わす、我々夫婦二人だった。
シルバーパスを持っているので、これを最大限に活用しようと、練馬春日町から新宿まで大江戸線。新宿から都営新宿線で西大島へ。そこから都バスで亀戸天神の前まで行った。バス停にバスの現在の運行状況が標示され、音声の案内までありびっくりした。亀戸天神は初めてで、特別広い、大きな神社ではなかったが、心字池がありそこに三つの橋が架かっていた。その三つの橋は、「過去、現在、未来」を意味するそうで、昨年屋号を「三世房」と変更した、三世 すなわち 過去・現在・未来と同じなのだ。過去・現在・未来を大切にとの思いで橋を渡ることができた。池の縁に鳥がいた。そばにいた人に聞いてみると、ゴイサギだと教えてくれた。あまり動かなかったが、真っ白な鷺ではなく白い体に紫色の頭・翼もあり、なかなか綺麗な鳥だった。そして真っ青に澄み渡った空に、スカイツリーが間近に見えた。
神殿の前や、社務所の前は受験生が沢山いた。40年ほど前に、九州の大宰府天満宮へ行った時のことが思い出された。何かのついでに一人で行ったのだが、確か白馬がいた記憶がある。そしてその時はさらに足を延ばして都府楼跡まで出向いたのも思い出した。ふと、とうりゃんせという童謡に、「行きはよいよい帰りは怖い」というフレーズが有るが、なぜ天神様にお参りするのに、怖い思いをしなければいけないのか私には意味不明なのだが・・・。
お昼を参道の店の十割ソバを食べ、葛餅を買い帰ろうとしたが、地図にある葛湯の店亀屋泉堂へ行きたいというので立ち寄ってみた。鹿児島の葛だそうで、手に持っていたく葛餅に葛は、は入っていないと言っていた。こういう話はよくある話で、キジ弁当にキジの肉は使われていないのだ。亀戸梅屋敷でまた手みやげを買い、ぶらぶら歩いて亀戸駅まで来た。またおなかがすいて、喫茶店でコーヒーにサンドイッチを頂いて、JRで両国に。両国駅もがらっと変わって、真新し綺麗なショッピング街が出来上がっていた。妻が折角だからと江戸東京博物館へ行きたいという。3時を回っていたがまあいいかと思って、「戦国時代展」を見る。戦国時代の鎧兜、絵図 書状などが展示してあった。織田信長の手紙を見て、これくらいのものが扱える古本屋になれればと、つい古本屋目線で見てしまった。
数日して信長の書状でないが、朝日新聞社発行の限定版の「川上澄生作品集」を買って頂いたお客様から、その後本物の版画が欲しいといわれ、彼の私家版の「御朱印船」(毛筆署名いり、手彩色入木版画6図 )
を買って頂いた。嬉しい思いをさせて頂いた。
今年の初詣は、地元の春日神社と亀戸天神へ行ってきた。毎年長男の家族と一緒のお参りだが、今年は春日神社へは一緒に行けたが、亀戸天神は日程が合わす、我々夫婦二人だった。
シルバーパスを持っているので、これを最大限に活用しようと、練馬春日町から新宿まで大江戸線。新宿から都営新宿線で西大島へ。そこから都バスで亀戸天神の前まで行った。バス停にバスの現在の運行状況が標示され、音声の案内までありびっくりした。亀戸天神は初めてで、特別広い、大きな神社ではなかったが、心字池がありそこに三つの橋が架かっていた。その三つの橋は、「過去、現在、未来」を意味するそうで、昨年屋号を「三世房」と変更した、三世 すなわち 過去・現在・未来と同じなのだ。過去・現在・未来を大切にとの思いで橋を渡ることができた。池の縁に鳥がいた。そばにいた人に聞いてみると、ゴイサギだと教えてくれた。あまり動かなかったが、真っ白な鷺ではなく白い体に紫色の頭・翼もあり、なかなか綺麗な鳥だった。そして真っ青に澄み渡った空に、スカイツリーが間近に見えた。
神殿の前や、社務所の前は受験生が沢山いた。40年ほど前に、九州の大宰府天満宮へ行った時のことが思い出された。何かのついでに一人で行ったのだが、確か白馬がいた記憶がある。そしてその時はさらに足を延ばして都府楼跡まで出向いたのも思い出した。ふと、とうりゃんせという童謡に、「行きはよいよい帰りは怖い」というフレーズが有るが、なぜ天神様にお参りするのに、怖い思いをしなければいけないのか私には意味不明なのだが・・・。
お昼を参道の店の十割ソバを食べ、葛餅を買い帰ろうとしたが、地図にある葛湯の店亀屋泉堂へ行きたいというので立ち寄ってみた。鹿児島の葛だそうで、手に持っていたく葛餅に葛は、は入っていないと言っていた。こういう話はよくある話で、キジ弁当にキジの肉は使われていないのだ。亀戸梅屋敷でまた手みやげを買い、ぶらぶら歩いて亀戸駅まで来た。またおなかがすいて、喫茶店でコーヒーにサンドイッチを頂いて、JRで両国に。両国駅もがらっと変わって、真新し綺麗なショッピング街が出来上がっていた。妻が折角だからと江戸東京博物館へ行きたいという。3時を回っていたがまあいいかと思って、「戦国時代展」を見る。戦国時代の鎧兜、絵図 書状などが展示してあった。織田信長の手紙を見て、これくらいのものが扱える古本屋になれればと、つい古本屋目線で見てしまった。
数日して信長の書状でないが、朝日新聞社発行の限定版の「川上澄生作品集」を買って頂いたお客様から、その後本物の版画が欲しいといわれ、彼の私家版の「御朱印船」(毛筆署名いり、手彩色入木版画6図 )
を買って頂いた。嬉しい思いをさせて頂いた。
カテゴリ:書物のまほろば
2016.10.31
第二次世界大戦中の知られざる活動 ドキュメンタリー映画「ウォーナーの謎のリスト」を見て
第二次世界大戦中の知られざる活動
ドキュメンタリー映画「ウォーナーの謎のリスト」を見て
ウォーナーの謎のリスト ~日本を愛した男たちがいた~という、ドキュメンタリー映画が完成した。
私は、2年ほど前、金髙謙二監督の前作「疎開した40万冊の図書」を、練馬のココネリで上映されたときに、見ることができた。(練馬の区立の複数の図書館が合同で主催)太平洋戦争時、東京が空襲になるというので、大八車やリュックに詰めて、人力で40万冊もの本を疎開させた時の記録映画だ。この映画を見て私は、古本屋としてもっと本を大切にしなくてはならないとつくづく思い知らされたものでした。
今回の映画に関連しては、以前から、第二次世界大戦時、アメリカ軍は、金沢、京都などの由緒ある建造物は爆撃を避けたとか、神保町の古本屋街も同じように空襲を避けたというような話は聞いていた。今回は、このアメリカ軍の日本爆撃の真相に迫った作品である。
第二次世界大戦中、日本の文化財を救おうとした外国人、一人は、アメリカ人美術家ランドン・ウォーナー。彼は日本において空爆すべきでない151か所のリスト「ウォ-ナーリスト」を作成した人物。もう一人は、親日家のロシア人セルゲイ・エリセーエフ。夏目漱石の門下で、神田神保町が空襲を受けなかったのは、彼の関与によるものとされる。彼らの行動を中心に、当時の状況を積み重ねていった作品である。
国内外で広範な取材活動をされ証言を集めて映画を造り上げて行き、真相に迫っている。ウォーナーの息子カレブ・ウォーナーは、米軍の戦略的爆撃と無差別爆撃法について「父は、標的は選んで爆撃すべきだとアドバイスしていた」と証言。セルゲイの義理の娘・歴史学者ダニエル・エリセーエフは、父について「彼の頭の中では、戦争に導いた軍国主義者と日本国民を混ぜてはならないという意識があった。」と証言している。
ウォーナーとイェール大学教授朝河貫一が組んで、戦争回避のための大統領から天皇への親書を創案したが、親書が天皇の元に届いたのは、1941年12月8日午前3時であったこと。 さらに、エピソードとして、吉祥寺の藤井書店の初代が招集された岩国で、本好きで神保町に毎日通ったという上官に出会い、彼一人だけ戦地への出兵を免れ、生きて帰れたという話も紹介されている。
創作意図として、金髙謙二監督は、次のように書いている。少し長いが引用させて頂く。
「戦争は狂気である」我師、新藤兼人はこの言葉を腹に据え100歳まで映画を撮り続けた。2001年3月、タリバンによるバーミヤン遺跡の大佛破壊、2015年2月、過激派組織IS(イスラム国)によるユネスコ世界遺産登録されている古代ローマの首都ハトラの破壊。戦争は殺戮以外に人間の尊厳となる文化遺産をも破壊し続けてきた。異国の文化とは言え、人類共通の財産のはずである。
この題材を通して、第二次世界大戦中に日本の文化財保護のために奔走した人々の想いの一端にふれてみたい。彼らは単に文化財だけを救おうとしたのか?それは人間を救うことにつながらないのか?そして、戦争回避につながらないのか?(中略)
文化財は、人類誕生600万年のDNAが受け継がれた結晶である。その国の文化財の中には、人間の歴史、生活、生き方、考え方すべてが詰まっている。文化を残すとは、人類の叡知、そして心を後世に継承することだと思う。
前作「疎開した40万冊の図書」にも沢山の古書店同業者の名前が登場したが、今回も
前述の藤井書店さん以外に八木書店、小宮山書店 中尾書店、キクオ書店 板橋書店 氷川書房、北澤書店 の皆さんが登場している。
さて、ウォーナーやエリーセーエフらの活動が、実際どの程度、アメリカ軍の戦闘行為に影響を与えたのか、与えなかったのか それはこの映画を見て究明して頂こうと思う。
いずれにしろ、文化財を破壊し、人命を奪い、歴史を抹殺する戦争という行為は、あってはならないものである。
ドキュメンタリー映画「ウォーナーの謎のリスト」を見て
三世房(サンゼボウ) 市 川 均
ウォーナーの謎のリスト ~日本を愛した男たちがいた~という、ドキュメンタリー映画が完成した。
私は、2年ほど前、金髙謙二監督の前作「疎開した40万冊の図書」を、練馬のココネリで上映されたときに、見ることができた。(練馬の区立の複数の図書館が合同で主催)太平洋戦争時、東京が空襲になるというので、大八車やリュックに詰めて、人力で40万冊もの本を疎開させた時の記録映画だ。この映画を見て私は、古本屋としてもっと本を大切にしなくてはならないとつくづく思い知らされたものでした。
今回の映画に関連しては、以前から、第二次世界大戦時、アメリカ軍は、金沢、京都などの由緒ある建造物は爆撃を避けたとか、神保町の古本屋街も同じように空襲を避けたというような話は聞いていた。今回は、このアメリカ軍の日本爆撃の真相に迫った作品である。
第二次世界大戦中、日本の文化財を救おうとした外国人、一人は、アメリカ人美術家ランドン・ウォーナー。彼は日本において空爆すべきでない151か所のリスト「ウォ-ナーリスト」を作成した人物。もう一人は、親日家のロシア人セルゲイ・エリセーエフ。夏目漱石の門下で、神田神保町が空襲を受けなかったのは、彼の関与によるものとされる。彼らの行動を中心に、当時の状況を積み重ねていった作品である。
国内外で広範な取材活動をされ証言を集めて映画を造り上げて行き、真相に迫っている。ウォーナーの息子カレブ・ウォーナーは、米軍の戦略的爆撃と無差別爆撃法について「父は、標的は選んで爆撃すべきだとアドバイスしていた」と証言。セルゲイの義理の娘・歴史学者ダニエル・エリセーエフは、父について「彼の頭の中では、戦争に導いた軍国主義者と日本国民を混ぜてはならないという意識があった。」と証言している。
ウォーナーとイェール大学教授朝河貫一が組んで、戦争回避のための大統領から天皇への親書を創案したが、親書が天皇の元に届いたのは、1941年12月8日午前3時であったこと。 さらに、エピソードとして、吉祥寺の藤井書店の初代が招集された岩国で、本好きで神保町に毎日通ったという上官に出会い、彼一人だけ戦地への出兵を免れ、生きて帰れたという話も紹介されている。
創作意図として、金髙謙二監督は、次のように書いている。少し長いが引用させて頂く。
「戦争は狂気である」我師、新藤兼人はこの言葉を腹に据え100歳まで映画を撮り続けた。2001年3月、タリバンによるバーミヤン遺跡の大佛破壊、2015年2月、過激派組織IS(イスラム国)によるユネスコ世界遺産登録されている古代ローマの首都ハトラの破壊。戦争は殺戮以外に人間の尊厳となる文化遺産をも破壊し続けてきた。異国の文化とは言え、人類共通の財産のはずである。
この題材を通して、第二次世界大戦中に日本の文化財保護のために奔走した人々の想いの一端にふれてみたい。彼らは単に文化財だけを救おうとしたのか?それは人間を救うことにつながらないのか?そして、戦争回避につながらないのか?(中略)
文化財は、人類誕生600万年のDNAが受け継がれた結晶である。その国の文化財の中には、人間の歴史、生活、生き方、考え方すべてが詰まっている。文化を残すとは、人類の叡知、そして心を後世に継承することだと思う。
前作「疎開した40万冊の図書」にも沢山の古書店同業者の名前が登場したが、今回も
前述の藤井書店さん以外に八木書店、小宮山書店 中尾書店、キクオ書店 板橋書店 氷川書房、北澤書店 の皆さんが登場している。
さて、ウォーナーやエリーセーエフらの活動が、実際どの程度、アメリカ軍の戦闘行為に影響を与えたのか、与えなかったのか それはこの映画を見て究明して頂こうと思う。
いずれにしろ、文化財を破壊し、人命を奪い、歴史を抹殺する戦争という行為は、あってはならないものである。
カテゴリ:書物のまほろば
2016.02.19
脚立から落ちて、骨折しました。
骨折記
今年の9月23日に、玄関の植木を剪定中、脚立から墜落して、頭を3針縫い、背骨を1か所と、右足かかとを骨折。つくづく馬鹿なことをした、大失敗と反省しきりでした。息子の車に乗せてもらい、休日診療をしている近所の病院で、頭のCTや足のレントゲンをとってもらった。その結果は頭の中身は大丈夫でしょうという事になり、かかとが、もしかして骨折しているかもしれない。明日はこの病院は休みだから、近所のクリニックにもう一度診てもらった方が良いと紹介状を書いてくれた。翌24日近所のクリニックに行ったら木曜日でお休み。木曜日は休診の医者が多い。そこで、ふと「休みだと言われた病院だが、病院は木曜日に休む訳がない」と思い、病院に電話をしてもらったら、もちろんやっていた。何か狐につままれた思いで病院に連れて行ってもらったが、整形外科の先生は、レントゲン写真を見ながら「大丈夫でしょう、普通に歩くようにしてみてください。」と言われ、「背中も痛いんですが」というと「せっかく紹介状があるんだから、このクリニックで見てもらったら」と振られてしまい、翌25日に近所のクリニックへ。レントゲンを撮り直してもらい、結果、かかとの骨折と背骨の骨折が判明。「かかとは絶対つけないで」と病院の医者とは逆のことを言われ、町医者のおかげで私は適切な治療をすることができた次第なのです。
「3か月ぐらいかな」との話。つまり完治まで3か月と理解して、鎧のようなコルセットに、足首には副木をあて、松葉杖の不自由な生活を強いられることになったのです。
パソコン
怪我をして、ネットの仕事は中断しようかと思ったが、妻もなんとかやってみるというので、それではこのまま続行してみようという事になった。しかし私が事務所の2階に上がることは困難で、いろいろ考えたが、パソコン1台を自宅のリビングに移動して、事務所から無線ランで飛ばしてみようと考えた。息子に設定を頼んで、パソコンを立ち上げたら、見事につながって動くではないか。結構、結構と喜んでいたが実際使ってみると、これが繋がって動く時と、全然だめな時があって頭を抱えた。設定の仕方が悪いのではとも考えた。たまたまパソコン修理屋さんが、レコードを市場で売ってくれないかと尋ね来たので聞いてみると、「無線ランは一軒の建物内なら問題ないが、たとえすぐ隣りの家でも外気に触れるとうまくいかない」といわれてしまった。事務所と自宅は道路一つ隔てただけなのだが・・・ 仕方なく、毎日パソコンのご機嫌をうかがいながら、パソコンと格闘している状況なのです。
風に立つライオン
怪我をして数日たち、少し余裕が出てきたので、本を読むことにした。倉庫に行けば本は売るほどあるのだか、自宅にはあまりない。そこで手あたり次第という言葉のとおり、棚の中で目に入った本から読むことにした。まず「風に立つライオン さだまさし著 幻冬舎刊 2013年発行」を読んだ。今年の父の日に娘から贈ってもらったが、目も通さずそのままにしていた本だ。実在の柴田紘一郎医師がモデルのようで、ケニアにある長崎大学熱帯医学研究所に出向して、風土病や南スーダンの内戦で負傷をした兵士や子どもたちの治療にあたった人物で、その人となりについて周囲の人間が話しを進めていく、というスタイルとなっている。彼が面倒を見たケニアの子どもが、大人になって医者となり、ボランテアとして津波で被災した宮城で日本人の中に入り込んで治療に当たるといった話があり、涙を流しながら読んだ本で、どこまでが、本当の話かわからないが、さすがにシンガーソングライターだけあって、ストーリーの展開が上手だなと感心したものでした。
厚生年金基金解散通知
私が属している年金基金から、表書きに「基金制度に関する重要なお知らせです。必ずお読みください」と書かれた封書が届いた。一瞬「来たな」との思いがよぎった。封書を開けてみると予想通りで、「厚生年金基金の解散方針の議決について」の書類だ。去年、AIJ投資顧問会社の詐欺事件で知ったのは、厚生労働省の役人が各年金基金に天下りをしており、彼らは資金運用については全くの素人で、証券会社にまかせっきりの結果の事件と聞いて亜然としたのだが、そのときは、「当年金基金は、問題ない」との連絡だったのだ。しかし事件により改正法が国会で成立して、基金の存続基準が厳しくなり、結果、解散方針が議決されたとのこと。今後は基金の上乗せ支給部分がなくなり、国の制度に一本化されるそうだ。
現政権は、株価対策で年金を運用しており、その運用成績はこの7-9月で10兆円近いマイナスだとか、私たちの老後はどうなるのだろうか。子どもの貧困問題も拡大しており、どうもこの国は弱者から目をそむけている国となってしまったようだ。
コールラビ
御近所に、出版プランナーいう名刺を持った方がいる。某出版社を定年退職した後にも、いろいろな本作りに携わっている方だ。彼から、時々古書の処分を依頼されているのだが、新潟のお土産と言って、お煎餅とりんごとへんてこりんな野菜をいただいた。宇宙人の頭みたいな格好の代物である。(宇宙人は見たことがない) 彼自身「自分は名前が分からないが、若い人なら知ってるのでは」と言っていた。2階の長男の嫁に聞くと「コールラビ」じゃないかといった。そこでパソコンで調べてみる。原産地は地中海北部。大根のようなブロッコリーのような味、とのとこ。大坂の二女に妻が電話をしていたので、聞いてみてもらうと、「コールラビは、ドイツにいた時よく食べていた」とのこと。大根は高いのに比べコールラビは1個30円くらいで買えたので、よく買って煮物にして食べたとのことだった。私は、大根は、煮るより漬物の方が好きなので、漬物にしてもらったが、大根よりスジっぽい感じがした。
入園試験
わが家は2世帯住宅である。今日は2階の孫の入園試験。3番目の末っ子で3歳。どう
みても甘やかされている。入園試験で、子どもたちは親から離され、男の子女の子別に集められたそうだ。そこで孫は大泣きをして、「バカ、バカ、バカ」と先生の顔を、なんども叩いたそうだ。嫁は落ちたかもしれないといって、家に帰ってきた。孫は家に帰って、嫁に向かって言ったそうだ。「幼稚園でね、泣かなかった子もいたんだよ、偉いね」と。
フォルテオ
11月6日、レントゲン検査の結果、足首は骨に多少のヒビが残っている程度で改善。そろそろ右足に体重を少しずつかけて、歩く練習のスタートをと言われた。一方、背骨は5mm沈んでいるといわれてしまった。前かがみになっては絶対ダメと言われており、そのためにきつめのコルセットを造ったと言われてしまった。私の素人判断だが、いい気になってパソコンをいじって、コルセットをしていても、結局前かがみの姿勢が悪かったのではと反省。そういえば、乳首がコルセットに当たり、スレて痛くて脹れあがってきてしまった。何もしないで、しばらく寝ていれば、こんなことにならなかったのでは・・・
結果として、フォルテオという皮下注射を、毎日2年間続けるはめになった。 さてその皮下注射だが、看護師さんから丁寧な説明を受けた。毎日自分でお腹または太ももに注射、その注射の位置は前日の注射位置から15センチ以上離すこと、その注射液は常温では効果がなくなってしまうので必ず冷蔵庫で保管すること。旅行など出かける時には、保冷バックにいれて、持ち運びをし、旅館についたらすぐに冷蔵庫にいれる事・・・これは大変だ。
「老夫婦」 絵ガブリエル・バンサン 詞ジャック・ブレル 今江祥智 訳BL出版刊
以前お客様から買い取った本の中の1冊で、「老夫婦」という本が目にとまった。最初はちらっと見て、年寄りが出てくるだけで、面白くない、売れそうにない本だ、と思ってテーブルのわきに放置しておいたが、放置しているのでまた目に留まる。ページをめくってみると、老夫婦、それも超高齢で、そろそろお迎えが来るであろう年頃の日常のデッサンなのだ。本の帯に「一世を風靡した歌手ジャック・ブレルのシャンソンにバンサンの絵筆が新たな息吹を吹き込んだ。バンサンが見つめる終焉の光と影」とあった。最初の絵には、「年老いたふたりには、いまはもう話すこともなく、ときおり、おたがいにそっと目をやるばかり」というシャンソンの冒頭が、キャプションとなっていた。人間誰しも、高齢になった時の生き様を、容赦なくとらえているのである。私にとってもそんなに先の話ではなくもうすぐ迎える世界、目をそむけることのできない世界を突き付けられたのだった。
でも、私には、もうちょっとエネルギーがあるような気がする。いつまでできるかわからないが、この怪我をばねにして、もう少し力を発揮して仕事を続けてみたいと考えるようになった。
彫刻家の平櫛田中さんは、「七十、八十は鼻たれ小僧、男盛りは百歳、百歳」と言っている。
今年の9月23日に、玄関の植木を剪定中、脚立から墜落して、頭を3針縫い、背骨を1か所と、右足かかとを骨折。つくづく馬鹿なことをした、大失敗と反省しきりでした。息子の車に乗せてもらい、休日診療をしている近所の病院で、頭のCTや足のレントゲンをとってもらった。その結果は頭の中身は大丈夫でしょうという事になり、かかとが、もしかして骨折しているかもしれない。明日はこの病院は休みだから、近所のクリニックにもう一度診てもらった方が良いと紹介状を書いてくれた。翌24日近所のクリニックに行ったら木曜日でお休み。木曜日は休診の医者が多い。そこで、ふと「休みだと言われた病院だが、病院は木曜日に休む訳がない」と思い、病院に電話をしてもらったら、もちろんやっていた。何か狐につままれた思いで病院に連れて行ってもらったが、整形外科の先生は、レントゲン写真を見ながら「大丈夫でしょう、普通に歩くようにしてみてください。」と言われ、「背中も痛いんですが」というと「せっかく紹介状があるんだから、このクリニックで見てもらったら」と振られてしまい、翌25日に近所のクリニックへ。レントゲンを撮り直してもらい、結果、かかとの骨折と背骨の骨折が判明。「かかとは絶対つけないで」と病院の医者とは逆のことを言われ、町医者のおかげで私は適切な治療をすることができた次第なのです。
「3か月ぐらいかな」との話。つまり完治まで3か月と理解して、鎧のようなコルセットに、足首には副木をあて、松葉杖の不自由な生活を強いられることになったのです。
パソコン
怪我をして、ネットの仕事は中断しようかと思ったが、妻もなんとかやってみるというので、それではこのまま続行してみようという事になった。しかし私が事務所の2階に上がることは困難で、いろいろ考えたが、パソコン1台を自宅のリビングに移動して、事務所から無線ランで飛ばしてみようと考えた。息子に設定を頼んで、パソコンを立ち上げたら、見事につながって動くではないか。結構、結構と喜んでいたが実際使ってみると、これが繋がって動く時と、全然だめな時があって頭を抱えた。設定の仕方が悪いのではとも考えた。たまたまパソコン修理屋さんが、レコードを市場で売ってくれないかと尋ね来たので聞いてみると、「無線ランは一軒の建物内なら問題ないが、たとえすぐ隣りの家でも外気に触れるとうまくいかない」といわれてしまった。事務所と自宅は道路一つ隔てただけなのだが・・・ 仕方なく、毎日パソコンのご機嫌をうかがいながら、パソコンと格闘している状況なのです。
風に立つライオン
怪我をして数日たち、少し余裕が出てきたので、本を読むことにした。倉庫に行けば本は売るほどあるのだか、自宅にはあまりない。そこで手あたり次第という言葉のとおり、棚の中で目に入った本から読むことにした。まず「風に立つライオン さだまさし著 幻冬舎刊 2013年発行」を読んだ。今年の父の日に娘から贈ってもらったが、目も通さずそのままにしていた本だ。実在の柴田紘一郎医師がモデルのようで、ケニアにある長崎大学熱帯医学研究所に出向して、風土病や南スーダンの内戦で負傷をした兵士や子どもたちの治療にあたった人物で、その人となりについて周囲の人間が話しを進めていく、というスタイルとなっている。彼が面倒を見たケニアの子どもが、大人になって医者となり、ボランテアとして津波で被災した宮城で日本人の中に入り込んで治療に当たるといった話があり、涙を流しながら読んだ本で、どこまでが、本当の話かわからないが、さすがにシンガーソングライターだけあって、ストーリーの展開が上手だなと感心したものでした。
厚生年金基金解散通知
私が属している年金基金から、表書きに「基金制度に関する重要なお知らせです。必ずお読みください」と書かれた封書が届いた。一瞬「来たな」との思いがよぎった。封書を開けてみると予想通りで、「厚生年金基金の解散方針の議決について」の書類だ。去年、AIJ投資顧問会社の詐欺事件で知ったのは、厚生労働省の役人が各年金基金に天下りをしており、彼らは資金運用については全くの素人で、証券会社にまかせっきりの結果の事件と聞いて亜然としたのだが、そのときは、「当年金基金は、問題ない」との連絡だったのだ。しかし事件により改正法が国会で成立して、基金の存続基準が厳しくなり、結果、解散方針が議決されたとのこと。今後は基金の上乗せ支給部分がなくなり、国の制度に一本化されるそうだ。
現政権は、株価対策で年金を運用しており、その運用成績はこの7-9月で10兆円近いマイナスだとか、私たちの老後はどうなるのだろうか。子どもの貧困問題も拡大しており、どうもこの国は弱者から目をそむけている国となってしまったようだ。
コールラビ
御近所に、出版プランナーいう名刺を持った方がいる。某出版社を定年退職した後にも、いろいろな本作りに携わっている方だ。彼から、時々古書の処分を依頼されているのだが、新潟のお土産と言って、お煎餅とりんごとへんてこりんな野菜をいただいた。宇宙人の頭みたいな格好の代物である。(宇宙人は見たことがない) 彼自身「自分は名前が分からないが、若い人なら知ってるのでは」と言っていた。2階の長男の嫁に聞くと「コールラビ」じゃないかといった。そこでパソコンで調べてみる。原産地は地中海北部。大根のようなブロッコリーのような味、とのとこ。大坂の二女に妻が電話をしていたので、聞いてみてもらうと、「コールラビは、ドイツにいた時よく食べていた」とのこと。大根は高いのに比べコールラビは1個30円くらいで買えたので、よく買って煮物にして食べたとのことだった。私は、大根は、煮るより漬物の方が好きなので、漬物にしてもらったが、大根よりスジっぽい感じがした。
入園試験
わが家は2世帯住宅である。今日は2階の孫の入園試験。3番目の末っ子で3歳。どう
みても甘やかされている。入園試験で、子どもたちは親から離され、男の子女の子別に集められたそうだ。そこで孫は大泣きをして、「バカ、バカ、バカ」と先生の顔を、なんども叩いたそうだ。嫁は落ちたかもしれないといって、家に帰ってきた。孫は家に帰って、嫁に向かって言ったそうだ。「幼稚園でね、泣かなかった子もいたんだよ、偉いね」と。
フォルテオ
11月6日、レントゲン検査の結果、足首は骨に多少のヒビが残っている程度で改善。そろそろ右足に体重を少しずつかけて、歩く練習のスタートをと言われた。一方、背骨は5mm沈んでいるといわれてしまった。前かがみになっては絶対ダメと言われており、そのためにきつめのコルセットを造ったと言われてしまった。私の素人判断だが、いい気になってパソコンをいじって、コルセットをしていても、結局前かがみの姿勢が悪かったのではと反省。そういえば、乳首がコルセットに当たり、スレて痛くて脹れあがってきてしまった。何もしないで、しばらく寝ていれば、こんなことにならなかったのでは・・・
結果として、フォルテオという皮下注射を、毎日2年間続けるはめになった。 さてその皮下注射だが、看護師さんから丁寧な説明を受けた。毎日自分でお腹または太ももに注射、その注射の位置は前日の注射位置から15センチ以上離すこと、その注射液は常温では効果がなくなってしまうので必ず冷蔵庫で保管すること。旅行など出かける時には、保冷バックにいれて、持ち運びをし、旅館についたらすぐに冷蔵庫にいれる事・・・これは大変だ。
「老夫婦」 絵ガブリエル・バンサン 詞ジャック・ブレル 今江祥智 訳BL出版刊
以前お客様から買い取った本の中の1冊で、「老夫婦」という本が目にとまった。最初はちらっと見て、年寄りが出てくるだけで、面白くない、売れそうにない本だ、と思ってテーブルのわきに放置しておいたが、放置しているのでまた目に留まる。ページをめくってみると、老夫婦、それも超高齢で、そろそろお迎えが来るであろう年頃の日常のデッサンなのだ。本の帯に「一世を風靡した歌手ジャック・ブレルのシャンソンにバンサンの絵筆が新たな息吹を吹き込んだ。バンサンが見つめる終焉の光と影」とあった。最初の絵には、「年老いたふたりには、いまはもう話すこともなく、ときおり、おたがいにそっと目をやるばかり」というシャンソンの冒頭が、キャプションとなっていた。人間誰しも、高齢になった時の生き様を、容赦なくとらえているのである。私にとってもそんなに先の話ではなくもうすぐ迎える世界、目をそむけることのできない世界を突き付けられたのだった。
でも、私には、もうちょっとエネルギーがあるような気がする。いつまでできるかわからないが、この怪我をばねにして、もう少し力を発揮して仕事を続けてみたいと考えるようになった。
彫刻家の平櫛田中さんは、「七十、八十は鼻たれ小僧、男盛りは百歳、百歳」と言っている。
カテゴリ:書物のまほろば
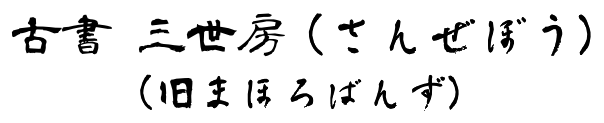
 RSS 2.0
RSS 2.0