2006.02.01
環境問題について
私たちの次世代に「美しい地球環境を残そう!」との思いで環境問題の関連書を、まほろばんず の1つの柱と考えました。
集めた本をジャンル別に、羅列してみますと、
地球温暖化 異常気象
大気汚染
環境ホルモン
科学物質 洗剤の毒性
遺伝子汚染
オゾンホール
環境破壊
森林破壊 植林
原発
グリーン電力
ゴミ
リサイクル
各地の問題・取り組み
水俣、足尾、神通川、北九州 琵琶湖 川崎 杉並 ドイツ チェルノブイリ アマゾン ベトナム
企業関連 環境マネジメント 環境会計 環境ビジネス
環境教育
などなど、現状野問題分析から対策まで雑多なタイトルの羅列ですが、実にさまざまな問題があることが分かります。
この2月に京都議定書が発効しました。これにより地球温暖化防止の第一歩として2008年から2012年の間に1990年排出量の6%減のレベルまで温室効果ガスを削減が定められています。6%達成のためには、国、企業活動やさらに私たち市民レベルの対応も大切です。
政府は4月には「京都議定書目標達成計画」を決定、その中で温室効果ガスの大規模排出源である企業向けの対策のほかに国民一人一人が省エネに取り組む重要性も訴えていえます。
政治のあり方、 行政のあり方、 これでもか、これでもかという不祥事が繰り返しされ、報道され続けていますが、国家百年の計よりの自分の利益であり、企業も相変わらずの利益至上主義が横行しています。
また、「一人一人の取り組みが大切」といっても実際は大変なことだと思われます。例えば、ゴミ問題一つとっても、指定された日に指定されたようにキチンと分別して出す人、いいがげんな人、資源ごみを勝手に持ち去る人、なるべくごみを減量しようと努力・実行している人そうでない人 様々です。
公務員・教職員の犯罪が増えているとか、私の住んでいる東京の練馬でも泥棒が多発するようになったとか、その犯罪が、低年齢化しているなどなど考えあわせますと、治安の良かった日本はどこへやらといった状況の中で、「一人一人の取り組み」の徹底は大変なことです。
たとえば、喫煙の問題で、「マナーからルールへ」とかっこいいキャッチフレイズで、禁煙やポイ捨ての区域が定められました。これは時代の流れなんでしょうが、すべてルール、決まり、条例、法律、罰則を設けないと問題が解決しないとなると、温室効果ガス削減について、市民として全体レベルの実行はなかなかむずかしいと思うのです。本当は差し迫った問題なのですが・・・ 太平洋上の島々では、温暖化→海面上昇→水没の危機が取りざたされています。
こうとらえてみると、やはり、根本的な私たちの生き方、生きる姿勢が大切に思われてきます。法律、罰則規定を強化ばかりでは問題解決にならず、人間はどのように生きるべきなのか考えてみますと、私たちは、この地球の自然ともに生きているのだし、その大自然の一部なのです。「 think globally act locally」 という言葉を新聞で見ましたが、自分の世界だけに埋没しないで、助け合い、支えあう生き方が大切との思うのです。
集めた本をジャンル別に、羅列してみますと、
地球温暖化 異常気象
大気汚染
環境ホルモン
科学物質 洗剤の毒性
遺伝子汚染
オゾンホール
環境破壊
森林破壊 植林
原発
グリーン電力
ゴミ
リサイクル
各地の問題・取り組み
水俣、足尾、神通川、北九州 琵琶湖 川崎 杉並 ドイツ チェルノブイリ アマゾン ベトナム
企業関連 環境マネジメント 環境会計 環境ビジネス
環境教育
などなど、現状野問題分析から対策まで雑多なタイトルの羅列ですが、実にさまざまな問題があることが分かります。
この2月に京都議定書が発効しました。これにより地球温暖化防止の第一歩として2008年から2012年の間に1990年排出量の6%減のレベルまで温室効果ガスを削減が定められています。6%達成のためには、国、企業活動やさらに私たち市民レベルの対応も大切です。
政府は4月には「京都議定書目標達成計画」を決定、その中で温室効果ガスの大規模排出源である企業向けの対策のほかに国民一人一人が省エネに取り組む重要性も訴えていえます。
政治のあり方、 行政のあり方、 これでもか、これでもかという不祥事が繰り返しされ、報道され続けていますが、国家百年の計よりの自分の利益であり、企業も相変わらずの利益至上主義が横行しています。
また、「一人一人の取り組みが大切」といっても実際は大変なことだと思われます。例えば、ゴミ問題一つとっても、指定された日に指定されたようにキチンと分別して出す人、いいがげんな人、資源ごみを勝手に持ち去る人、なるべくごみを減量しようと努力・実行している人そうでない人 様々です。
公務員・教職員の犯罪が増えているとか、私の住んでいる東京の練馬でも泥棒が多発するようになったとか、その犯罪が、低年齢化しているなどなど考えあわせますと、治安の良かった日本はどこへやらといった状況の中で、「一人一人の取り組み」の徹底は大変なことです。
たとえば、喫煙の問題で、「マナーからルールへ」とかっこいいキャッチフレイズで、禁煙やポイ捨ての区域が定められました。これは時代の流れなんでしょうが、すべてルール、決まり、条例、法律、罰則を設けないと問題が解決しないとなると、温室効果ガス削減について、市民として全体レベルの実行はなかなかむずかしいと思うのです。本当は差し迫った問題なのですが・・・ 太平洋上の島々では、温暖化→海面上昇→水没の危機が取りざたされています。
こうとらえてみると、やはり、根本的な私たちの生き方、生きる姿勢が大切に思われてきます。法律、罰則規定を強化ばかりでは問題解決にならず、人間はどのように生きるべきなのか考えてみますと、私たちは、この地球の自然ともに生きているのだし、その大自然の一部なのです。「 think globally act locally」 という言葉を新聞で見ましたが、自分の世界だけに埋没しないで、助け合い、支えあう生き方が大切との思うのです。
カテゴリ:書物のまほろば
2006.01.31
心の煤払い
年の瀬も押し詰まってくると「大掃除」という言葉が耳に入ってくる。我々日本人が、こういった季節ごとの節目を伝統的に大切にしているのは、本当に良いことだと思う。
以前、ご近所の奥さんが、久しぶりにフロ釜の掃除をしたら、真っ黒い煤のようなものがいっぱい出てきて、本当にすっきりしたというお話を伺ったことがあるが、掃除をすることによって、本人の心まですっきりと掃き清められるものなのだ。掃除は、まさしく“心の煤払い”である。その昔、お釈迦様の弟子のシュリハンドクという方は、お釈迦様から一本のほうきを与えられ、一生懸命掃除をした結果、悟りを得て、お釈迦様の十大弟子となった、という話を読んだことがあるが、なるほどとうなずける話である。
幸田文さんの随筆には、父・幸田露伴の躾について、書かれた文章がある。露伴は、刺した雑巾は好まず「刺し雑巾は不潔になりやすいし、性のないようなぼろっきれに丹念な針目を見せて、糸ばかり残るなんぞは、時間も労力の無益」といい、汚れた雑巾で拭いては、黒光りするだけだ、きれいな水でよく拭き込んだ廊下は「花がつお」のような色と照りがあると教え、雑巾のしぼり方から、はたきの使い方、ふすまの張替え、薪割り、さらに鋤や鍬の使いかたまで、“渾身” ということを教わったと記されている。
イエローハットという会社を起こされた鍵山社長は、実にこの掃除の実践で、大きな会社を作り上げた。会社から最寄駅まで毎日掃除する話は、有名な話だが、鍵山社長の掃除をしている姿に感心した人から土地・建物の提供を受けた話など鍵山社長の著書「凡事徹底」(致知出版社)に詳しい。 あちこちで講演会も開いておられた。 掃除を大切にした松下幸之助さんや、丸井の青井社長、セブンイレブン、ディズニーランド 花王などなど多くの会社が、掃除を大切にしている。
私は、以前武道館の周辺の道路を掃除したことがあったが、タバコの吸殻の多いのにはびっくりした。「マナーからルールへ」というかっこいいキャッチフレイズがあるが、すべて規則とか罰則とかで規制しないとダメだという状況が、残念な思いだった。が、吸殻のあまりの多さに規則・罰則も現実的な対応で、やむなしと思うようになった。
家の周辺を掃除しても、このタバコとさらに犬の糞にお目にかかる。日本人の公徳心はどこへ言ってしまったのだろうと思ったりもするのだが、幼稚園の園児たちと「おはようございます」と挨拶を交わし、落ち葉なども、掃き清めるとすっきりとしたきもちで、仕事に取り組めるのだ。 事務所や倉庫のあふれている本の山を速やかに片付け、キチンと掃除をして、心を磨がいて仕事を進めたい。
掃除については、以下の二冊があった。
たかが掃除と言うなかれ 山本健治著 1996年 日本実業出版社
掃除が変わる会社が活きる 山本健治著 1995年 日本実業出版社。
以前、ご近所の奥さんが、久しぶりにフロ釜の掃除をしたら、真っ黒い煤のようなものがいっぱい出てきて、本当にすっきりしたというお話を伺ったことがあるが、掃除をすることによって、本人の心まですっきりと掃き清められるものなのだ。掃除は、まさしく“心の煤払い”である。その昔、お釈迦様の弟子のシュリハンドクという方は、お釈迦様から一本のほうきを与えられ、一生懸命掃除をした結果、悟りを得て、お釈迦様の十大弟子となった、という話を読んだことがあるが、なるほどとうなずける話である。
幸田文さんの随筆には、父・幸田露伴の躾について、書かれた文章がある。露伴は、刺した雑巾は好まず「刺し雑巾は不潔になりやすいし、性のないようなぼろっきれに丹念な針目を見せて、糸ばかり残るなんぞは、時間も労力の無益」といい、汚れた雑巾で拭いては、黒光りするだけだ、きれいな水でよく拭き込んだ廊下は「花がつお」のような色と照りがあると教え、雑巾のしぼり方から、はたきの使い方、ふすまの張替え、薪割り、さらに鋤や鍬の使いかたまで、“渾身” ということを教わったと記されている。
イエローハットという会社を起こされた鍵山社長は、実にこの掃除の実践で、大きな会社を作り上げた。会社から最寄駅まで毎日掃除する話は、有名な話だが、鍵山社長の掃除をしている姿に感心した人から土地・建物の提供を受けた話など鍵山社長の著書「凡事徹底」(致知出版社)に詳しい。 あちこちで講演会も開いておられた。 掃除を大切にした松下幸之助さんや、丸井の青井社長、セブンイレブン、ディズニーランド 花王などなど多くの会社が、掃除を大切にしている。
私は、以前武道館の周辺の道路を掃除したことがあったが、タバコの吸殻の多いのにはびっくりした。「マナーからルールへ」というかっこいいキャッチフレイズがあるが、すべて規則とか罰則とかで規制しないとダメだという状況が、残念な思いだった。が、吸殻のあまりの多さに規則・罰則も現実的な対応で、やむなしと思うようになった。
家の周辺を掃除しても、このタバコとさらに犬の糞にお目にかかる。日本人の公徳心はどこへ言ってしまったのだろうと思ったりもするのだが、幼稚園の園児たちと「おはようございます」と挨拶を交わし、落ち葉なども、掃き清めるとすっきりとしたきもちで、仕事に取り組めるのだ。 事務所や倉庫のあふれている本の山を速やかに片付け、キチンと掃除をして、心を磨がいて仕事を進めたい。
掃除については、以下の二冊があった。
たかが掃除と言うなかれ 山本健治著 1996年 日本実業出版社
掃除が変わる会社が活きる 山本健治著 1995年 日本実業出版社。
カテゴリ:書物のまほろば
2005.12.01
呼吸法
2000年の11月にインターネットの古書店を開業させて頂いた。丁度その頃、関節リウマチになった。手の指が脹れてきたのだ。駅前の整形外科に行って、検査の末に間接リウマチと診断され、治療の難しい、膠原病じゃなくてよかったですねとも言われた。
関節リュウマチと診断されて、家族から専門医に診てもらった方が良いのでは、と言われ、ネットで、リウマチ友の会という存在を知った。そこに電話をして相談したら、練馬という立地から、新宿の大きな大学病院を教えて頂いた。この病院には、「膠原病リウマチ痛風センター」というのがあり、これらの病気に関しては、日本では、一番大きな規模の病院ではないかと思う。診察室が15ぐらいあり、とにかく患者も先生も多いのだ。
この病院に月一回の割合で、もう4年も通っているのだが、この間に色々なことがあった。通院して1年以上たって、2回目のレントゲンを撮った。その結果を見て、先生は、にっこり笑いながら、「やっぱり関節リウマチですね。」と言った。にっこり笑ったのは、自分の診断に間違いはなかったということで、思わず、にっこりしたのだろうが、私にとっては、たとえ誤診であっても、もっと簡単に直る病気の方が嬉しかったのだが・・・。 レントゲンで見る指の骨が、以前と比べると少し欠けていたのだった。
そして、薬の副作用には、随分と悩まされた。診察室の壁に模造紙が貼ってあり、そこに沢山のリウマチ薬のサンプルが貼りつけてある。その中で患者の症状にあわせて、弱い薬から強い薬を選択していくのだ、私は、薬の影響でしょっちゅう、気持ち悪くなったり、吐き気がしたりして事務所で寝込んでしまったことも何回かあった。 その都度薬を替えてもらうのだが、何度目かに、副作用を訴えると、先生曰く、「どうしましょうか?」ときたのだ。私はこの言葉に、一瞬「頼りにならない先生だと」という思いだった。しかし時間がたつにつれ、現代に医療姿勢は、患者の意思を尊重するものであり、患者の考えを確認したうえで、対処するのでは、と思うようになり、あわせて病気は医者が治すのではなく患者本人の病気に対する気持ちが大切と思うようになった。つまり、人まかせでなく、自分の病気は自分で直すという気構えが一番肝心なのだと悟ったものでした。
リウマチがなかなか直らない病気であることを体験して、民間の治療法にもトライしている。今迄試したものは、あざらしのオイル(オイルシール)、サメの軟骨、アロエべラ、核酸などなど。他には、鍼、ラジウム、温泉など今後色々トライしてみたいと思っている。
そんな折に“呼吸法”で、病気が良くなるという言葉を耳にした。そこで、「丹田呼吸法」 村木弘昌著 三笠書房刊 を読んでみた。 心臓病、糖尿病、ガンなど万病に良いとされるこの、丹田呼吸法は、遠くお釈迦様に起因するのだそうだ。お釈迦様は、色々荒行を試みたがこれらの行が、悟りとは無縁であることを知り、かくして、菩提樹の下に座すこと三か月、悟りを得る。このときの呼吸法が、「出る息を長く吸う方は短く」という呼吸法だったそうだ。
この本では、さらに白隠禅師の「夜船閑話(やぜんかんな)」にふれ、内観法、軟酥の法にふれている。軟酥の法は、まさしくイメージトレーニングである。白隠禅師は、これを、山城の国の山奥に住んでいる白幽仙人から教わり、これを実行することによって、鍼も灸もいらないと言っているのだ。
私は、この本の中で紹介されている一番簡単な「三呼一吸法」を毎日続けている。まだ始めて二か月。発病以来四年もたっているので、すぐに直るわけはない。「継続は力なり」で、続けている。
なおこの本のなかでも、紹介されていた、西野バレー団の西野皓三著「西野流呼吸法」 講談社刊、や龍村修著「深い呼吸でからだが変わる」など呼吸法は人間の健康、活力と大いにかかわっているのだということが良く分かった。
関節リュウマチと診断されて、家族から専門医に診てもらった方が良いのでは、と言われ、ネットで、リウマチ友の会という存在を知った。そこに電話をして相談したら、練馬という立地から、新宿の大きな大学病院を教えて頂いた。この病院には、「膠原病リウマチ痛風センター」というのがあり、これらの病気に関しては、日本では、一番大きな規模の病院ではないかと思う。診察室が15ぐらいあり、とにかく患者も先生も多いのだ。
この病院に月一回の割合で、もう4年も通っているのだが、この間に色々なことがあった。通院して1年以上たって、2回目のレントゲンを撮った。その結果を見て、先生は、にっこり笑いながら、「やっぱり関節リウマチですね。」と言った。にっこり笑ったのは、自分の診断に間違いはなかったということで、思わず、にっこりしたのだろうが、私にとっては、たとえ誤診であっても、もっと簡単に直る病気の方が嬉しかったのだが・・・。 レントゲンで見る指の骨が、以前と比べると少し欠けていたのだった。
そして、薬の副作用には、随分と悩まされた。診察室の壁に模造紙が貼ってあり、そこに沢山のリウマチ薬のサンプルが貼りつけてある。その中で患者の症状にあわせて、弱い薬から強い薬を選択していくのだ、私は、薬の影響でしょっちゅう、気持ち悪くなったり、吐き気がしたりして事務所で寝込んでしまったことも何回かあった。 その都度薬を替えてもらうのだが、何度目かに、副作用を訴えると、先生曰く、「どうしましょうか?」ときたのだ。私はこの言葉に、一瞬「頼りにならない先生だと」という思いだった。しかし時間がたつにつれ、現代に医療姿勢は、患者の意思を尊重するものであり、患者の考えを確認したうえで、対処するのでは、と思うようになり、あわせて病気は医者が治すのではなく患者本人の病気に対する気持ちが大切と思うようになった。つまり、人まかせでなく、自分の病気は自分で直すという気構えが一番肝心なのだと悟ったものでした。
リウマチがなかなか直らない病気であることを体験して、民間の治療法にもトライしている。今迄試したものは、あざらしのオイル(オイルシール)、サメの軟骨、アロエべラ、核酸などなど。他には、鍼、ラジウム、温泉など今後色々トライしてみたいと思っている。
そんな折に“呼吸法”で、病気が良くなるという言葉を耳にした。そこで、「丹田呼吸法」 村木弘昌著 三笠書房刊 を読んでみた。 心臓病、糖尿病、ガンなど万病に良いとされるこの、丹田呼吸法は、遠くお釈迦様に起因するのだそうだ。お釈迦様は、色々荒行を試みたがこれらの行が、悟りとは無縁であることを知り、かくして、菩提樹の下に座すこと三か月、悟りを得る。このときの呼吸法が、「出る息を長く吸う方は短く」という呼吸法だったそうだ。
この本では、さらに白隠禅師の「夜船閑話(やぜんかんな)」にふれ、内観法、軟酥の法にふれている。軟酥の法は、まさしくイメージトレーニングである。白隠禅師は、これを、山城の国の山奥に住んでいる白幽仙人から教わり、これを実行することによって、鍼も灸もいらないと言っているのだ。
私は、この本の中で紹介されている一番簡単な「三呼一吸法」を毎日続けている。まだ始めて二か月。発病以来四年もたっているので、すぐに直るわけはない。「継続は力なり」で、続けている。
なおこの本のなかでも、紹介されていた、西野バレー団の西野皓三著「西野流呼吸法」 講談社刊、や龍村修著「深い呼吸でからだが変わる」など呼吸法は人間の健康、活力と大いにかかわっているのだということが良く分かった。
カテゴリ:書物のまほろば
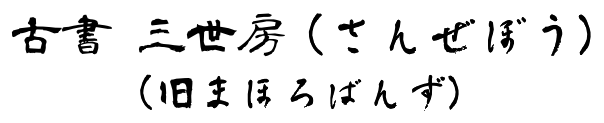
 RSS 2.0
RSS 2.0